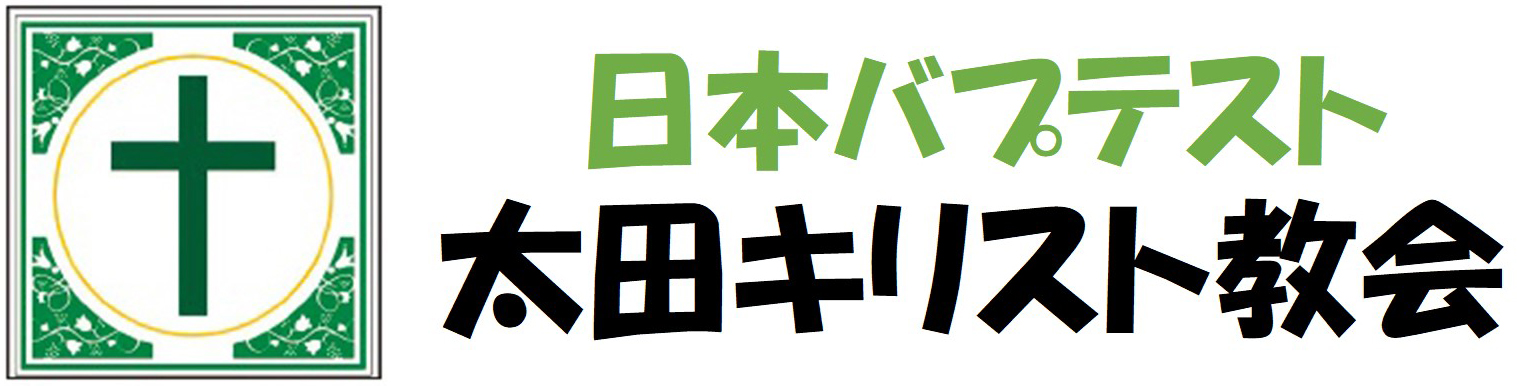礼拝メッセージ(2025年10月26日)「こちらと向こうを隔てる壁」ヨナ書4:1~11

誰の滅びも望まない神様の想い
ヨナ書の最後の場面になりました。ニネベの人々はヨナの預言を聞いて悔い改め、悪の道を離れました。すると神様はニネベに災いをくだすことを思い直されました。たくさんの人々が災いから逃れることができたのですから、それでハッピーエンドといきたいところですが、そうはいきません。なぜなら、このことがヨナにとって大いに不満だったからです。
ヨナはニネベのことを憎んでいました。ニネベが以前に自分たちを侵略した国の都だったからです。ヨナはニネベが滅びればいいと思っていました。神様から災いをくだされるべきだと思っていました。でも、そうはならなかった。ヨナは怒りに燃え、神様に不平を言いました。ニネベが助けられ、これからもニネベの人々が生き続けるなら、いっそのこと私は生きているより死んだ方がましです、とさえ言いました。
預言者であるヨナは、神様が「恵みと憐れみの神であり、忍耐深く、慈しみに富み、災いをくだそうとしても思い直される方」であることを知っていました。ついこの間、ヨナ自身が神様に背き、命を失いそうになりながら、神様によって助けられ、神様の恵みと憐れみを、身をもって体験していました。でも、神様が恵みと憐れみをニネベの人々に向けることを、ヨナは決して受け入れようとはしませんでした。
「お前は怒るが、それは正しいことか。」(ヨナ書4章4節)
神様はヨナに問いかけました。神様の恵みと憐れみについて、こちら側と向こう側を隔てて考えようとすることは、正しいことか、と神様はヨナに考えさせようとしました。
ヨナは都の外に出て、そこに小屋を建てて座り込み、ニネベの様子をうかがっていました。すると神様はとうごまの木を生えさせ、ヨナの頭の上に木陰を作りました。熱い日差しがさえぎられたので、ヨナは喜び、一時は不満も消えました。
しかし翌日の明け方、神様は虫に命じてとうごまの木を食い荒らさせたので、木は枯れてしまいました。さらに日が昇ると、今後は焼け付くような熱風を吹きつけさせたので、ヨナはぐったりと弱り、再び不平を言いました。
「生きているより、死ぬ方がましです。」(ヨナ書4章8節)
「お前はとうごまの木のことで怒るが、それは正しいことか。」という神様からの再度の問いかけに、今度はヨナもすぐに答えました。「もちろんです。怒りのあまり死にたいくらいです。」(ヨナ書4章9節)
その怒りを否定せず、神様は続けて言いました。
「お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのとうごまの木さえ惜しんでいる。それならば、どうしてわたしが、この大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、十二万人以上の右も左もわきまえぬ人間と、無数の家畜がいるのだから。」(ヨナ書10~11節)
神様は誰の滅びも望みません。しかしヨナは自分とニネベの人たちの間に線を引き、神様の恵みと憐れみはこちら側だけに向けられることを求め、向こう側に向けられた神様の恵みと憐れみには怒りを抱きました。その怒りは正しいことだったのでしょうか。
「人間の分断」の原型となった「人と自然の分断」
人と人の間に線引きをすることは、今も様々なところで行われています。形を変えながら、ますます強まっているとさえ言えます。こちら側と向こう側の間には分厚い壁が立てられ、向こう側の人のことは何も知らないままで、警戒心や憎しみが募り、争いが引き起こされることが繰り返されてきました。
それと共に、人と自然の間にも線引きがなされています。この傾向は聖書を基盤とした西欧社会の中で強められ、広められてきたものです。神学者たちは、人間は自然や動物を支配する存在だと主張し、動物は理性や感情がない劣った存在だと決めつけてきました。そのことが、人間の利益のために自然や動物を利用することを正当化してきました。
人類学者の奥野克己さんは、今日の状況についてこのように書いています。
「人間は、地球上の多くの場所で、動植物やモノを含む自然を人間の領域から切り離 して対象化し、人間の利益と快適さのために自然を利用・改変しながら現代世界を作り上げた。よく言われるように、人の手によって地球環境の生態環境は台無しにされたのである。その結果、地球上のあらゆる生物が『傷ついた地球』に住まわざるを得なくなり、人間が自然から手痛いしっぺ返しを受けていることに、最近になってようやく気づくようになった。」(『今日のアニミズム』)
人間を自然や動物よりも優れたものだとする人間中心主義的な考え方は、人間の間に線引きをして、差別や支配を正当化することにもつながっています。人間中心主義は、男性中心主義や白人中心主義などに転用されました。そのとき、支配する側が理性的な人間であり、支配される側は自然に近く、理性が未発達だと勝手に決めつけられました。
そのような考え方は間違いでしたが、今でも無くなったわけではありません。差別はいけないこと、人権はすべての人がもっているものとされていますが、それでも差別はなくならず、人権は踏みにじられる。それはなぜだろうかと考えてきましたが、「優れた人間が劣った自然を支配する」という世界観も、その原因の一つになっているのかもしれません。
聖書と矛盾しないアニミズム的な世界観
人間の社会はすべてが人間中心の世界観を持っていたわけではありません。むしろ日本を含む多くの地域・民族では、それとは異なる「アニミズム的な世界観」をもっていました。キリスト教が世界に広められていくとき、宣教師たちはアニミズム的な世界観を「遅れたもの」や「偶像礼拝」、「迷信」として否定してきました。
しかし20世紀後半以降、自然との関係を支配ではなく、共生として理解しようとする流れが出てきました。また、アニミズム的な世界観を、神の被造物との霊的な関係として捉え直し、再評価するようにもなりました。「すべてのものが生きていて、すべてのものが人格であり、その一部のみが人間であるという新アニミズム的な世界観が旧約聖書の根底に横たわっている」と主張する神学者もいるほどです。
奥野さんは、「アニミズムとは『人間だけが地球上の唯一の主人(マスター)ではない』という考え方」だと説明しています。動物や植物も、自然界に存在するものは精神や内面性を持つ存在であり、人間と本質的には変わらない存在として見る。人間と自然・動植物との間に線引きをしない世界観。それがアニミズムだというのです。
アニミズムといっても、自然や動植物を神として見る、というわけではありません。ポイントは、人間が自然や動植物の主人ではない、ということだろうと私は理解しました。人間も自然や動植物と同じ被造物であり、互いに関わりあって生きている。そのような考えは、聖書に矛盾しないように思えます。
西欧のキリスト教社会では、人間も被造物の一つに過ぎず、他の被造物と関わり合って共に生きている、という世界観を捨ててしまいました。その結果、神様の創られた世界を壊し、人間も他の生き物も苦しんでいるわけです。そうだとすれば、西欧社会が作りだした人間中心の世界観は神様の教えから離れてしまったものであり、考え直す必要があるのではないか、と思っています。
壁は神様が作ったのではない
私は北海道に住んでいる間に、アイヌ文化を知る機会がありました。アイヌの伝統的な考え方では、身の回りのほとんどすべてのものが「カムイ」となります。犬も猫も、スズメやカラスも、木も草も、虫も火もカムイです。人間にできないことをするもの、人間の役に立ってくれるものはすべてカムイなので、食器などもカムイとなります。そして、それらのものすべてに魂がある、というのが基本的な考え方です。
「カムイ」とは「神」と訳されることがありますが、聖書で証しされる神とは違った存在です。ある人はカムイを「環境」と置き換えると納得しやすいと言っています。アイヌの考え方は、カムイと良い関係を結ぶことによって、アイヌもカムイも幸福な生活を保つことができる、というものです。アイヌ(=人間)とカムイ(=環境)はお互いを必要とするパートナーであり、人間は環境からの恩恵によって生きている。それを当たり前と思わずに感謝して受け取ることによって、環境を悪化させずに生きていくことができる。そのように説明されるとわかりやすいと思います。
このような世界観の下では、人間は自然の支配者ではありませんし、自然を壊すほどに利用することも控えられました。アイヌとカムイ、人間と自然はつながっていて、どちらにも魂があり、同じ人格を持った存在であり、共に生きるパートナーである。そのような考え方は、今の社会に必要なもののように思えます。創世記2章では、人間のパートナーの候補として、神様が野の獣や空の鳥を連れてきた、という記述もありました。
このような世界観でも、もちろん違いはあります。人間は自然や動植物とは違います。けれども、その線引きは本質的な違いではなく、上下や優劣でもありません。このような世界観のもとでは、差別や支配が正当化されにくかったようです。
ヨナ書からだいぶ離れてしまいましたが、改めて読み返すと、ヨナ書でも動物のことが語られています。ニネベの王は国中に断食を命じた時、人だけでなく、家畜も共に断食するように命じました。そして神様は、ニネベの人々だけでなく、そこで生きている無数の家畜の生命も惜しむと言っておられました。
今の世界では、人間と自然が線引きされ、人と人を隔てる壁が作られています。しかし神様は、人間が作った線も壁も関係なく、すべての人に恵みと憐れみを向け、同じようにすべての動物、植物、自然にも恵みと憐れみを向けられる方なのではないでしょうか。こちら側と向こう側を隔てる壁は、本来、存在しないものだった。神様が作られたわけでも、良しとされたわけでもなかった、ということを覚えていたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍・サイト
『現代聖書注解 ホセア書―ミカ書』J.リンバーグ、日本基督教団出版局、1992年
『今日のアニミズム』奥野克己・清水高志、以文社、2021年
『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』中川裕、集英社、2019年
Goldwin Field Reserch Lab.「わたしたち、以外の“わたしたち”へ 加速する現代社会とアニミズム/奥野克己(人類学者)」
https://fieldresearchlab.goldwin.co.jp/column/animism-03/、2025年6月20日
※Simone CappellariによるPixabayからの画像