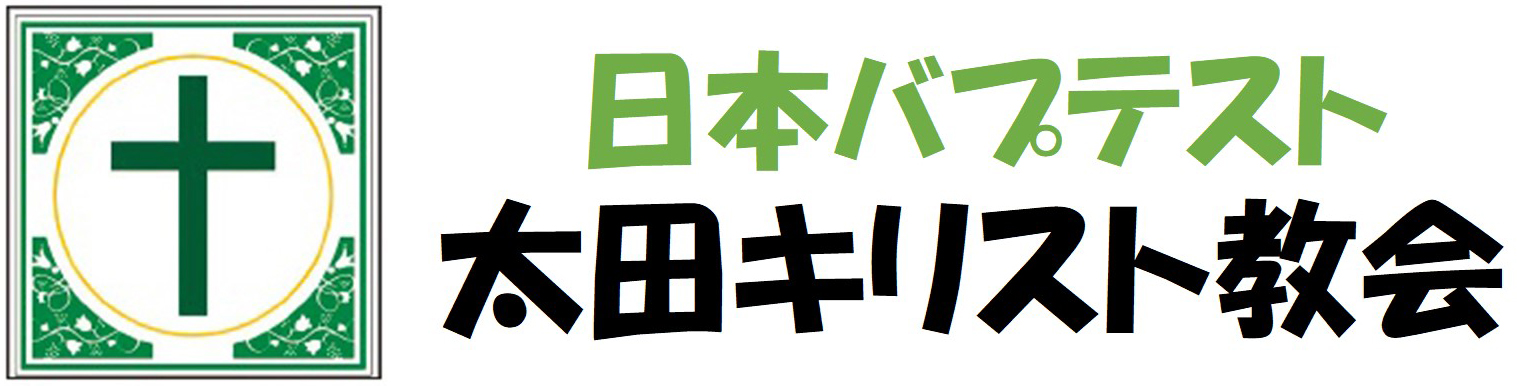礼拝メッセージ(2025年11月16日)「次に来てほしい世界」アモス書9章11~15節

裁きの後の、救いの約束
紀元前760年ごろ、北イスラエル王国で神様の言葉を伝えた預言者の一人にアモスという人がいました。彼はイスラエル王国の中で行われている罪を指摘して、神様からの裁きが降ることを告げました。国家の滅亡を預言したアモスは、祭司アマツヤによって国外追放されてしまったので、活動期間は1年ほどしかありません。それでもアモスの言葉は神様の言葉として覚えられ、語り継がれていきました。
それからおよそ200年後のこと。既に北イスラエル王国は滅びていました。同じ民族の南ユダ王国も滅ぼされ、国の中心人物がバビロンへ捕囚として連れ去られていました。アモスや他の預言者たちが警告したように、イスラエルの国はどちらも滅びてしまいました。
そのような中で、アモスの言葉を語り継いできた人たちは神様に問いかけました。預言が実現して、神様の裁きが行われた今、苦しみ、嘆き、不安を抱えている人たちに、神様は何と語られるのだろうか。預言者アモスが生きていたら、神様からどのような言葉を聞き、皆に告げるのだろうか。今日の箇所は、そのように問う人々に伝えられた神様の言葉です。
「裁き」は神様の最後の言葉ではありません。人間が罪を犯し、それによって裁きを受けたり、自ら災いを引き起こしたりしても、神様はその先に「救い」をもたらすことを目標としてくださいます。だから、アモスから200年後、国家の滅亡を経験した人々も、神様から救いの約束を聞くことができたのです。
楽園のような町
神様は、「廃墟となった町々を建て直し、囚われた人々を帰らせる」、と言われました。建て直される町は、まるで楽園のような場所となります。畑の麦は豊かに実り、それを刈り入れる人の後から、新たに種が蒔かれていきます。収穫が絶え間なく続くほど、豊かな実りが与えられ、黄金色に輝く麦畑が町を覆っています。
ぶどうの木も有り余るほどの実をつけています。収穫したぶどうは、岩をくりぬいた酒ぶねのなかで踏みつぶし、ぶどう汁を集めていました。集めたぶどう汁は発酵させてぶどう酒を作りました。神様によって建て直された町では、ぶどうの収穫があまりにも多いので、ぶどう汁は酒ぶねから溢れ、山肌を覆うように流れていきます。歌ったり、笑ったりしながら、ぶどうを潰していく人々の陽気な声が町の中に響いています。
人々は荒らされた町を建て直します。そこに自分たちで畑を作り、ぶどう園を作り、自分たちの手で得た収穫を食べて暮らします。生まれ育った土地に住み着き、そこから追いやられる心配もありません。お互いのことを知り合い、協力して生きていくことができる、安心・安全な町。生きるために必要なものが十分に得られ、誰も取り残されず、貧しさに苦しむ人がいない町。それが、神様が建て直すことを約束された、楽園のような町の姿です。
善が求められ、恵みの業が行われる次の世界
「昔の日のように建て直す。」(アモス書9章11節)
神様はそう語られました。しかしそれは、アモスが預言したときの北イスラエル王国を再び建てるということではないでしょう。裁きをもたらし、滅亡を引き起こしてしまった国は、次に来る世界にはふさわしくありません。
アモスの時代、イスラエルは国家としては繁栄し、大きな力を持っていました。しかし町の中では、貧しい人々が靴一足分の借金のために奴隷として売られ、家畜のように使い捨てられていました(2章6節)。国家の繁栄は、「不法と乱暴」(3章10節)の上に築かれており、誇るべきものは何もありませんでした。
財を成した商人たちは、「豪奢な寝台やダマスコ風の長いす」(3章12節)のような豪華な家具を備え付けた大邸宅に住み、自分の富を増し加えることばかり考えていました。貧しい人々を守るはずの法律はないがしろにされる一方、「正しい者に敵対し、賄賂を取り、町の門で貧しい者の訴えを退け」るという不公正な裁判を利用して、富が蓄積されていました(5章12節)。
神様はアモスを通してこのように告げていました。
「善を求めよ、悪を求めるな。」(5章14節)
「悪を憎み、善を愛せよ。」(5章15節)
「正義を洪水のように、恵みの業を大河のように、尽きることなく流れさせよ。」(5章24節)
神様が次にもたらそうとする世界は、格差と不公正による繁栄ではなく、善を求め、恵みの業が行われる世界です。その世界を創り出すことが神様の変わらない目標であり、そのために行われるのが救いの御業なのです。
封建社会の次に来た世界
私たちの暮らしている社会は「資本主義社会」ですが、近年、資本主義に対して疑問を抱いたり、否定的な考えを持ったりする人が増えているようです。2020年に行われた調査では、世界の過半数の人が、「資本主義は良いことより悪いことの方が多い」と考えていることがわかりました。また最近では、資本主義の総本山ともいうべきアメリカのニューヨーク市で、社会主義者だと自称するマムダニ氏が市長に選ばれる、ということも起こりました。
私も資本主義の問題点を学び始めていて、『資本主義の次に来る世界』(ジェイソン・ヒッケル著)という本も読みました。その中で、今日の預言の内容とも重なるような出来事が書かれていましたので、ご紹介したいと思います。
舞台は中世のヨーロッパです。当時は封建社会と呼ばれる体制で、領主が土地を支配し、そこに住む農奴は地代(借地料)や様々な税金を負担させられていました。1300年代の初めに、ヨーロッパの各地で農奴が反乱を起こし始めました。税金を納めることを拒否するものや、軍事衝突に発展するものなどがありましたが、始めの頃は領主の軍隊によって鎮圧されていました。
1347年、黒死病(腺ペスト)が流行し、未曽有の危機に襲われます。ヨーロッパ人口の3分の1が死亡したため、労働力が不足し、結果として労働者側が交渉力を持つようになりました。その中で反乱は勢いを増して拡大していき、最終的にはヨーロッパの大部分で農奴制は廃止されました。農奴は自由農民となり、封建制に代わる新しい社会を作り始めたそうです。
「自給自足を原則とする平等で協働的な社会だ。この改革は、平民の福利に驚くべき影響を及ぼした。賃金のレベルは歴史上かつてないほど上昇し、ほとんどの地域で2倍から3倍になり、6倍になるケースもあった。地代は下がり、食料は安くなり、栄養状態は向上した。労働者は、労働時間の短縮や週末の休暇、さらには、仕事中の食事や、職場への交通費などについて交渉できるようになった。女性の賃金も上昇し、封建制度下では顕著だった男女の賃金格差は狭まっていった。歴史家は、この1350年から1500年までを「ヨーロッパ労働者階級の黄金時代」と呼ぶ。」(『資本主義の次に来る世界』P.50~51)
この変化を読みながら、私は今の社会に必要とされているものと似ていると思いました。このような社会は、アモス書で語られた楽園のような町ほど豊かではありませんが、その方向に向かおうとするものでもあったのではないでしょうか。
次に来てほしい世界
この「平等で協働的な社会」を終わらせたものが「資本主義」でした。封建社会の中で富を蓄えてきた貴族、教会、商人たちは協力して農民の自治を終わらせ、賃金を引き下げようとしました。牧草地や森林、川などは私有財産とされ、自給自足の生活が不可能にされました。ヨーロッパ各地で数百万人の人々が土地から追い出され、国内避難民となりました。
資本主義は大衆を貧困化させることによって生まれました。1500年代から1700年代にかけて、実質賃金は70%も減りました。栄養状態も悪化し、飢餓が広がりました。イングランドでは、1500年代に43歳だった平均寿命が、1700年代には30歳にまで低下しました。資本主義は、大衆を貧困化させることで、上流階級が富を蓄積できるようにしたのです。
今の世界が続いてほしいと思うか、それとも違う世界に代わってほしいと思うか。あるいは変わるとしても、次に来る世界がどのようなものであってほしいのか、ということは、社会的な地位によっても変わるのでしょう。ヨーロッパの農民が望み、勝ち取った世界は、領主など上流階級の者たちにとっては邪魔な物もの、すぐにでも終わらせたいものでした。
アモス書の最後に書き加えられた預言は、神様が滅亡の次にもたらそうとした世界を語っています。しかしそれは、誰もが待ち望む世界ではありません。イスラエル王国で上流階級だった人たちは、そんな世界を望まず、過去のイスラエル王国が取り戻されることを望んだことでしょう。国や町の中でどれほど貧しい人々がいて、どれほど苦しんでいようとも、国が繫栄し、自分たちの富が増し加えられる世界が、彼らにとって望ましいものだったからです。
神様が約束された世界を望んだのは、貧しくされてきた人々だったのではないでしょうか。富も地位もなく、搾取と暴力の中で苦しめられてきた人々は、自分たちを苦しめてきた国家が滅亡したとき、次に来てほしい世界として、神様の預言を受け取ったのではないでしょうか。「平等で協働的な社会」が、神様が回復し、建て直す、次にもたらすと約束された世界なのではないか、と私は信じています。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍・サイト
『ATD旧約聖書註解(25)十二小預言書 上』A.ヴァイザー、ATD・NTD聖書註解刊行会、1982年
『資本主義の次に来る世界』ジェイソン・ヒッケル、東洋経済新報社、2023年
※Batatolis PanagiotisによるPixabayからの画像