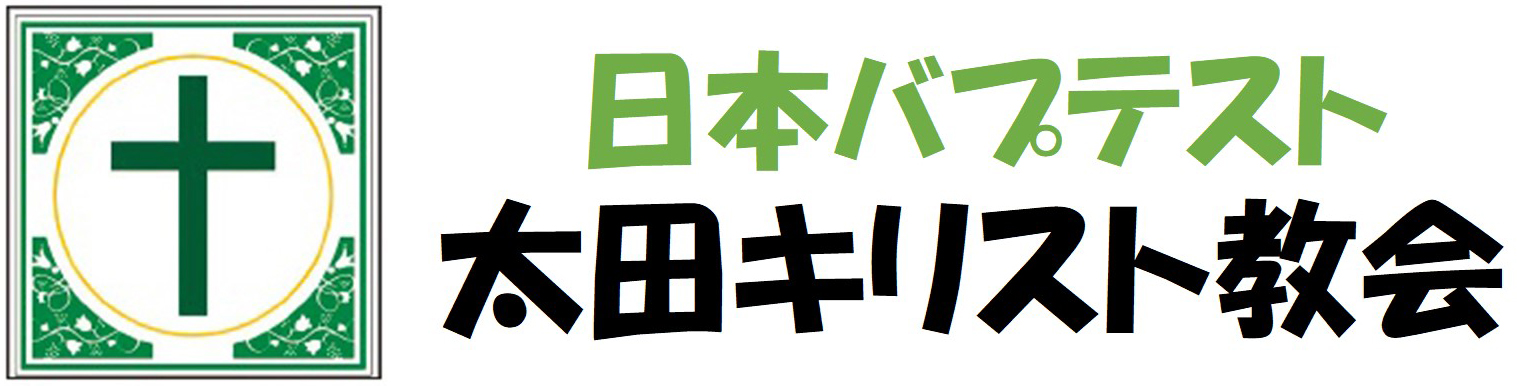礼拝メッセージ(2025年11月2日)「貧困を生み出す社会の否定」アモス書1章1節、2章6~16節

繫栄したイスラエルへの怒りの言葉
今から約2800年前、紀元前760年ごろのお話。その頃、パレスチナには南のユダ王国と北のイスラエル王国がありました。もともとは一つの国でしたが、ずいぶんと前に2つの国に分かれていました。
イスラエル王国はこれまでも繁栄と衰退を繰り返してきました。このころの王はヤロブアムⅡ世。彼は41年間、イスラエルの王であり、その間、王国は安定していて、とても繁栄しました。他国に奪われた領土も取り戻し、王国の国境線は、最も反映していたソロモン王の時代と同じところにまで拡げられました。イスラエルの人々は自信を取り戻し、再び訪れた平穏で繁栄した生活を楽しんでいました。
同じ時代、南のユダ王国にあるテコアという小さな町に、アモスという人が住んでいました。彼はたくさんの羊を飼っている資産家でもありました。ある時、彼が羊の群れを世話していると、神様の言葉が聞こえてきました。
「行って、わが民イスラエルに預言せよ」(アモス書7章15節)
神様はアモスに5つの幻を見せました。神様の言葉を聞き、幻を見たことで、アモスは北のイスラエル王国の人々に、神様の言葉を伝えることを決心しました。
アモスはユダ王国からイスラエル王国へとやって来ました。彼の目にも、その町はとても豊かな町に映ったことでしょう。人々は活気にあふれ、様々な物に満ちていました。ただ、そこに住んでいる誰もが豊かであったわけではありません。その様子を見て、アモスは神様の言葉を語るべきだと確信しました。それは優しく励ます言葉ではなく、厳しい告発の言葉でした。
「主はシオンからほえたけり/エルサレムから声をとどろかされる。」(アモス書1章2節)
ほえたけり、とどろくその声は、まるでライオンのうなり声のようでした。羊を飼っていたアモスは、ライオンに出くわしたこともあったでしょう。獲物に向かってほえたけるライオンの声を聞いたときの恐怖がよみがえるほど、イスラエルに向けられた神様の声も恐ろしいものでした。
イスラエルの人々は、アモスの言葉を聞いて驚き、戸惑い、あるいは怒りました。「自分たちはうまくいっている。戦いに勝利して、領土を取り戻した。国は再び繫栄して、豊かな生活ができている。今は平穏で、この生活がずっと続いていくこと、いや、もっと豊かになっていくことを信じている。」そのようにイスラエルの人々は思っていたからです。
しかしアモスは神様の怒りを伝えました。
「主はこう言われる。イスラエルの三つの罪、四つの罪のゆえにわたしは決して赦さない。」(アモス書2章6節)
それはまるで、ライオンがほえるような怒りの声でした。
神様の怒りの理由――犠牲と不正
イスラエルの町には、繁栄して平穏な生活を送っている人がいる一方で、貧しく、取り残された人たちもいました。イスラエルでも格差が拡大し、多くの物を持っている人と、わずかな物も取り上げられる人に分け隔てられていました。繁栄も、平穏も、貧しい人たちには関係ないもの、手の届かないものになっていました。
権力を持った人々は、持っている物を分かち合うどころか、さらに多くの物を求めてより一層、貪欲になっていました。貧しい人々は借金を負わされ、その返済が滞れば奴隷として売られたり、家畜のように扱われたりしました。それも靴一足を買えるくらいのわずかな借金のために、奴隷として売られたのです。
繁栄して見えたイスラエルの社会は、神様の目には腐敗したものに見えました。その腐敗は神殿にも及んでいました。借金の担保として貧しい人々から取り上げられた衣服が、礼拝の儀式のために使われ、同じように取り上げられたぶどう酒が、神殿で捧げる供え物とされました。神様に捧げるものは傷の無い、浄いものでなければならないのに、貧しい人々を貶めて、奪い取った物、社会の腐敗にまみれた物が使われていたのです。
アモスより20年ほど後の預言者イザヤも、イスラエルの罪を告発しました。
「災いだ、偽りの判決を下す者/労苦を負わせる宣告文を記す者は。
彼らは弱い者の訴えを退け/わたしの民の貧しい者から権利を奪い
やもめを餌食とし、みなしごを略奪する。」 (イザヤ書10章1~2節)
腐敗したイスラエルでは、法律も弱い人や貧しい人を守らないで、金持ちや権力者の利益のために歪められていました。判決は公平ではなく、力ある者に有利なように働き、力のない人の声は無視され、持っているはずの権利さえ奪われました。
確かにイスラエル王国は繁栄し、多くの人が平穏な生活を送っていました。けれどもその反面、格差は拡大し、不正が広がりました。借金を負わされ、貧しくされた人たちは、繁栄も平安もなく、むしろその犠牲とされ、見捨てられていました。神様が怒り、ライオンの吠える声のような怒りの言葉を聞かせたのには、このような背景がありました。
貧困を生み出さない社会へ
アモスは神様からの告発と共に、神様がどのような方であるかを思い出させようとすることも伝えました。それは、神様がイスラエルの祖先をエジプトから導き出した方である、ということです。
「お前たちをエジプトの地から上らせ/四十年の間、導いて荒れ野を行かせ
アモリ人の地を得させたのはわたしだ。」(アモス書2章10節)
イスラエルの祖先はエジプトで奴隷とされていました。エジプトの繁栄のために厳しい労働をさせられ、助けを求めて叫んでいました。イスラエルの人々の貧しさは、当時のエジプトの社会制度によって人工的に作り出されたものでした。そのようなところから神様はイスラエルの人々を助け出し、貧困から逃れさせたのです。
アモスにこのことを語らせた神様は、出エジプトの目的をイスラエルの人々に気づかせたかったのかもしれません。貧困から脱出したイスラエルが、新たな貧困を生み出すならば、それは神様の御心に適うものではありません。神様は貧困を生み出さない社会を新たに創り出そうとされておられるからです。
聖書に記された律法は、イスラエルの人々が新しく作る社会の形を示していました。それはイスラエルの人々が苦しめられてきたエジプトとは異なる社会。貧困がもはや存在しない新しい社会の姿を描いています。
神様は創造する方、新たに創り出す方です。混沌とした世界の中から新しい秩序を創り出すこと。格差や不正によって貧困を創り出す社会から脱出して、誰も犠牲にされず、一人も見捨てられない新しい社会を創り出すこと。それが、神様がイスラエルに与えた使命であり、イスラエルと共に歩む目的でした。
神様が創り出そうとする新しい社会では、貧困を生み出す社会の構造そのものが否定されています。国家の繁栄や平穏のために、誰かを犠牲にし、誰かを貧しくさせることそのものが否定されているのです。そのような繁栄や平穏は、神様から与えられたものではなく、神様に背く罪によって作られたものです。
今の社会からは想像しづらいかもしれません。けれども、人類が動物を狩り、植物を集めて生活していたときには、大きな格差はありませんでした。今も多くの先住民族の共同体は、平等な社会を作っています。
神様は貧困を生み出す社会を否定し、それに怒りを向けておられます。神様が求め、創り出そうとしておられるのは、貧困を生み出さない社会、平等な社会、共に生きられる社会なのです。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍・サイト
『現代聖書注解 ホセア書―ミカ書』J.リンバーグ、日本基督教団出版局、1992年
『ATD旧約聖書註解(25)十二小預言書 上』A.ヴァイザー、ATD・NTD聖書註解刊行会、1982年
『新共同訳 旧約聖書略解』木田献一監修、日本キリスト教団出版局、2001年
『反貧困の神――旧約聖書神学入門』ノルベルト・ローフィンク、キリスト新聞社、2010年
※iris VallejoによるPixabayからの画像