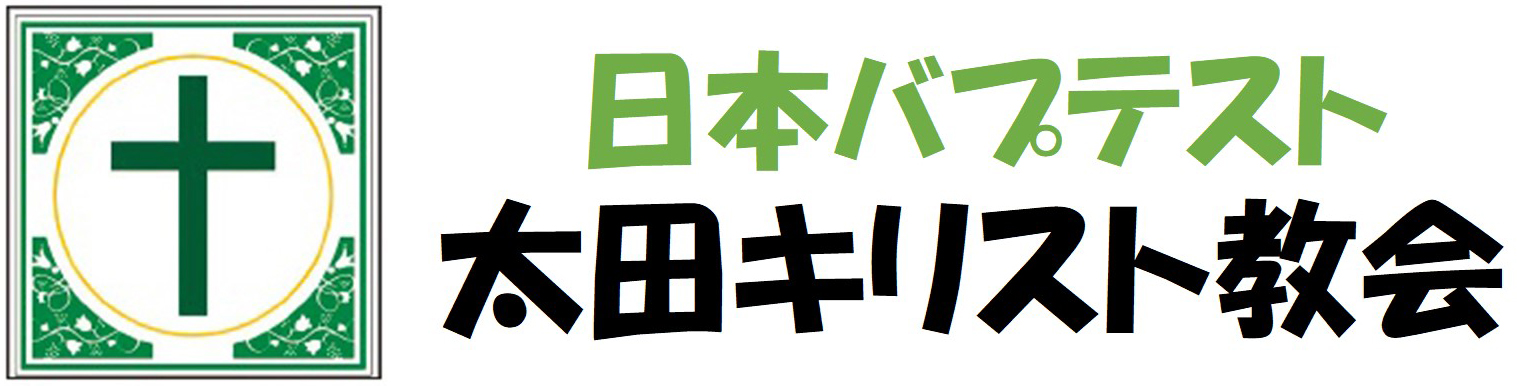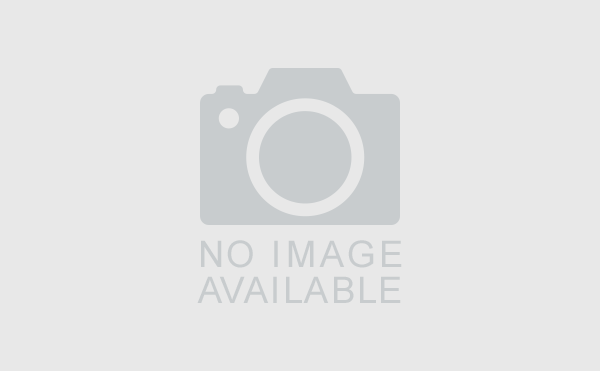礼拝メッセージ(2025年4月13日)「人の苦しみに身をさらす神」マタイによる福音書27:32~56
超越的な力への誘惑
本日から受難週が始まります。イエス・キリストが弟子たちも含めた人々から見捨てられ、苦しみを受け、十字架につけられて殺され、墓に葬られる出来事に思いを向ける期間です。教会は、イエスを神の子・救い主であると信じ、告白をしています。そのイエスが苦しみを受けたことの意味を、改めて覚えたいと思います。
神の子・救い主が来る、ということは、当時のユダヤの人々の誰もが信じていたことでした。イエスに期待していたユダヤの人々も、イエスを捕らえ、死刑にしようとした祭司長たちもそうでした。しかし、彼らが待っていた神の子・救い主と、苦しみを受けるイエスの姿は、まったく異なるものでした。そのことが、十字架に架けられたイエスに向けられた言葉から伝わってきます。
十字架の下を通りかかった人々は言いました。「神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い」(マタイによる福音書27:40)。また、祭司長たちもイエスを侮辱して言いました。「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば、今すぐ救ってもらえ。『わたしは神の子だ』と言っていたのだから」(マタイによる福音書27:42~43)。
彼らにとってみれば、神の子が苦しむなんてことは考えられないことでした。神の子は、この世の汚れからいっさい自由である聖なる者だから、この世の苦しみとは無縁だと思っていたのです。また、人々を救い、解放する救い主が、自分を苦しみから救えない無力な存在であるということも想像できないことでした。救い主は超越的な力でこの世を支配する王のような存在だと信じていたからです。
待ち望んでいる神の子・救い主へのそのような期待は、祭司長たちも、ユダヤの民衆も、そしてイエスの弟子たちも持っていました。圧倒的な力を持った神の子・救い主への期待の裏には、自分自身も圧倒的な力を持ちたい、という願いがあったのかもしれません。
それは過去のことではなく、今も少なくない人が実現させようとしている願いかもしれません。世界規模で極端な格差が拡大し続けており、力を独占した一握りの人たちと、力を奪われた多くの人たちとに分断されています。圧倒的な力を持ちたいと願い続け、そのためにどんなことでもしようとしているのは、力を独占してきた一握りの人たちです。
しかしその願いには、悪魔の誘惑が入り込みます。マタイ福音書4章には、イエスが荒れ野で誘惑を受けられたことが書かれています。そのときの悪魔の誘惑は、超越的な力を用い、神を思いのままに動かし、世界を支配することをそそのかす、というものでした。イエスは悪魔の誘惑を退けましたが、その誘惑はいつの時代の人間にも有効でした。そしてその誘惑に陥っているときには、苦しむイエスは人からも神からも見捨てられた無残な脱落者としか思えなかったのです。
失われたものを取り戻したいという願い
悪魔の誘惑にそそのかされるような願い――超越的な力を得、この世を思いのままにしようとする願い――は、神に受け入れられるものではありません。しかし、人の願いそのものがすべて退けられるわけではなく、むしろ神は私たちが祈り願うことを求めておられます。
イエスも、「わたしの名によってわたしに何かを願うならば、わたしがかなえてあげよう」(ヨハネによる福音書14:14)と言っておられます。また、詩編37編4節でも、「主に自らをゆだねよ/主はあなたの心の願いをかなえてくださる」と呼びかけられています。
それでは、主が叶えようとされる願いとは、どのような願いなのでしょうか。イザヤ書58章10節では、このように言われています。
「飢えている人に心を配り/苦しめられている人の願いを満たすなら
あなたの光は、闇の中に輝き出で/あなたを包む闇は、真昼のようになる。」
苦しめられている人の願いが満たされるなら、暗闇に光が輝く。苦しめられている人の願いこそ、主が叶えようとする願い、イエスが「かなえてあげよう」と言われる願いなのではないでしょうか。既に大きな力を持ちながら、それを増し加えようとするときの苦しみではなく、持っているはずの力を奪われ、苦しみを負わされている人の願いを、主は聞いておられるのです。
超越的な力を求めされる悪魔の誘惑は、その誘惑に陥った人を罪に陥れるだけではありません。力を独占しようとするならば、それは他の人々から力を奪うことになります。イエスの時代に、ローマ皇帝が力を独占し、支配した人々を抑圧し、搾取し、生きる力を奪ったように、今も多くの人が力を奪われ、苦しみを負わされています。
そのようなときに抱く願いは、悪魔の誘惑のような不遜な願いではなく、失ったものを取り戻したいという願いなのではないでしょうか。人並みに生きたいとか、健康で平安な日々を送りたいとか、毎日おいしいご飯を食べたいとか。そのようなささやかな願いすら叶わない現実を押しつけられてしまう。イエスの時代のガリラヤの人々もそうでした。
失われたものを取り戻したいという願いは、イエスの願いでもありました。
「人の子は、失われたものを捜して救うために来たのである。」(ルカによる福音書19:10)
神様は私たち人間を含むあらゆる被造物を創造し、それを祝福されました。ご自身が与えた祝福が奪われることを、神様は放っておくことができません。だから、再び祝福が与えられるために、生命が守られるために、失われたものが取り戻されるために、神の子イエス・キリストがこの世に来られたのです。
苦しみを味わいつくしたその先に
苦しみを負わされた人々を何とかして救いたい。それが神様の想いであり、イエスの願いです。それでも、私たちの願い――苦しむ人々の願い――が、いつも思い通りに叶えられるわけではありません。イエスも苦しみから逃れたいと祈り願いましたが、最後には神の御心に委ね、苦しみを負わされました。
イエスは弟子たちに見捨てられ、兵士たちに侮辱され、祭司長たちにはののしられ、苦しみぬいて十字架の上で、大声で叫び、死にました。「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」(マタイによる福音書27:46)という叫びは、神にさえ見捨てられたイエスの絶望を訴える叫びでした。
このとき、神はどこにいたのでしょうか。天の彼方の玉座から、このようすを眺めていたのでしょうか。いいえ、そうではありません。この十字架で死んだ人・イエスは本当に神の子だったのです。この世で最も低くされたところ、苦しみのすべてを負わされるところ、絶望の十字架にこそ、神はいたのです。耐えきれないような苦しみを負わされたとき、神はその人と共にいて、共に叫んでいるのです。
苦しみを負わされた人が絶叫するとき、神は天の彼方に座ってはいられずに、地に降り、人の苦しみにその身をさらし、共にその苦しみを味わいつくす。そのような信仰は、聖書の神への信仰に受け継がれてきました。神は人が苦しむことを望んではおられない。けれども、この世で生きるとき、自分では避けられない苦しみを負わされることがある。そのときには、神もまた共に苦しみに身をさらしておられます。それほどまでに、神は私たちの近くにおられるのです。
神の目的は、苦しみを共にすることではなく、そこからの解放であり、失われたものを取り戻すことです。イエスの十字架も、それがゴールなのではありません。けれども、復活は、十字架の死の後に起こされます。イエスが告げ知らせた福音、身をもって表された神の国の実現は、神が苦しみを味わいつくしたその先に起こされるのです。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988