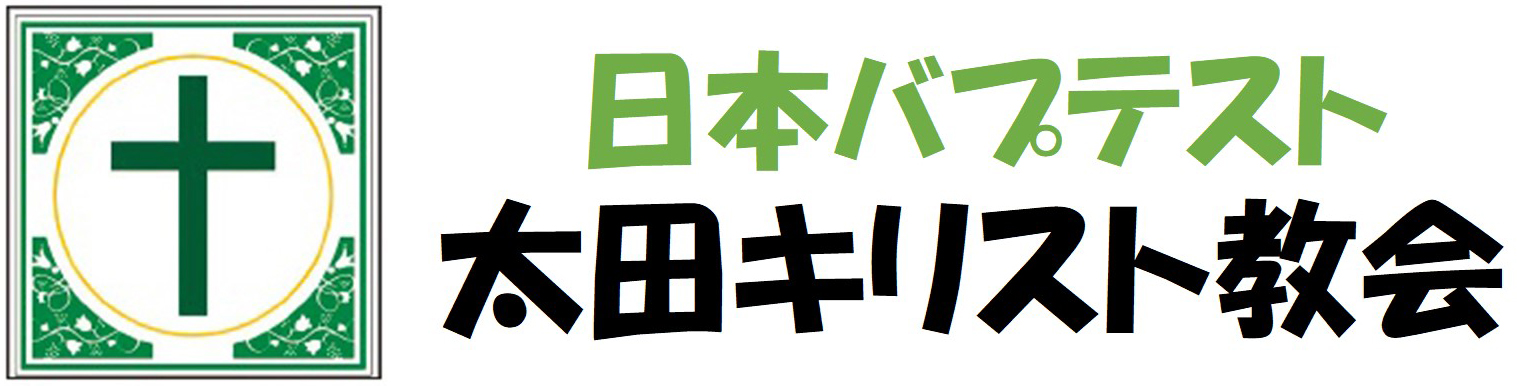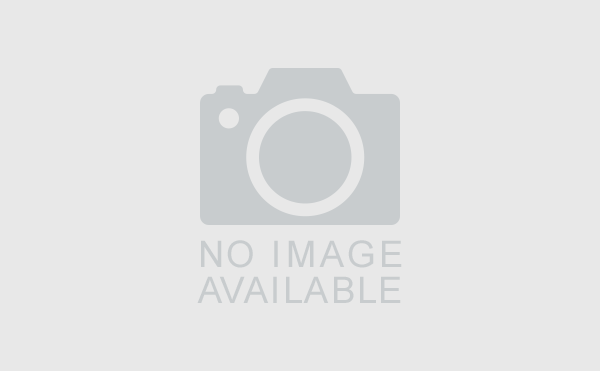礼拝メッセージ(2025年4月20日イースター)「世界を分かち合う」マタイによる福音書28:1-10
悲しみが喜びに変えられる
イースターは、キリスト教会にとってクリスマスと同じくらいか、あるいはそれ以上に重要な日です。最近では、身の回りでも「イースター」の文字を見ることが多くなってきました。先日、“100均”に行きましたら、そこにもイースター関連の商品が並べてありました。ただ、そのようなところでは、あくまで「ヨーロッパの春祭り」としてイースターが受け止められているように思えます。
イースターとは、イエス・キリストの復活を祝う日であり、日本語では「復活祭」とも呼ばれます。この世に一人の人として生まれたナザレのイエスが、十字架に架けられて死んでから三日目によみがえった、ということを記念した日です。そのイエスは神の子・救い主であった。イエス・キリストが死に、そして死からよみがえった、という信仰によって、キリスト教は始まりました。
イエスの十字架の死は、あまりにも無残で、人から罵られ、苦しめられるものでした。十字架にかけられたその姿は、神にさえ見捨てられたように見えました。弟子たちは、敵対者に捕らえられ、何の抵抗もなさらないイエスを見捨てて、逃げ去ってしまいました。十字架での死を最後まで見守っていたのは、イエスに従って歩んできたマグダラのマリアたち、数人の女性だけでした。
イエスは金曜日の午後3時ごろに息を引き取られました。その後、夕方には墓に葬られましたが、その様子もマリアたちが見守っていました。もう夜になります。土曜日はユダヤ教では安息日であったため、家に帰らなければなりません。イエスの死のショックを抱えながら、最後のお別れもできずに安息日を過ごし、日が明けた日曜日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアがイエスの墓へ向かいました。
するとそこに天使が天から降ってきて、二人のマリアにこう告げたのです。
「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」(マタイによる福音書28:5~6)
二人のマリアは恐れながらも、この知らせに大いに喜び、弟子たちに知らせるために急いで走っていきました。すると、行く手にイエスが立っていました。イエスは二人に「カイレテ」とあいさつをしました。「カイレテ」というのは、「喜び」という意味を持ったあいさつの言葉です。十字架で悲しみ、苦しみ、希望を失っていた二人のマリアに、「喜びなさい!」とイエスは語りかけたのです。
十字架では、イエスが神に見捨てられたように見えたけれども、神はイエスを見捨ててはいなかった。イエスはこの世の苦しみを負い、人びとの罪を担って死なれたけれども、死は終わりではなかった。神は世の苦しみにその身をさらし、人びとの罪を赦し、新しい世界を創り出してくださる。イエスが宣べ伝えたように、神の国が、今ここに、やってきている。そこではもう悲しむことはない。誰も神から見捨てられない。一人にはされない。新しい世界が始まる。だから「喜びなさい」と呼びかけられている。それが復活の出来事でした。
人の支配とは異なる神の支配(神の国)
このとき、天使とイエスは二人のマリアに弟子たちへの伝言を託しました。それは、「ガリラヤへ行きなさい」という伝言でした。弟子たちはガリラヤで復活されたイエスと会うことになる。なぜ、エルサレムではなく、ガリラヤだったのでしょうか。ガリラヤとはどのような場所なのでしょうか。
ガリラヤは、イエスと弟子たちが暮らしてきた場所であり、家族や友人がおり、イエスと弟子たちが出会い、福音を伝え、病を癒され、様々な奇跡を行った場所です。一方でガリラヤは、エルサレムの人々からは汚れた地として蔑まれており、ローマ帝国の支配下で、何重にも搾取され、抑圧されてもいました。
もともとは豊かな地であったガリラヤですが、何重もの搾取と抑圧のために多くの人が追い詰められていました。先祖伝来の土地を奪われたり、大切な家族を奪われたり、使い捨ての駒のように利用され、病や障がいを負わされたりする人が絶えませんでした。それに加えて、宗教的な清さを保てない「罪人」だと呼ばれて蔑まれました。
そのようなガリラヤで、イエスは弟子たちを招き、人びとを癒し、励まし、絆を結んでおられました。イエスは「神の国が近づいた」と教えました。「神の国」とは、「神の支配が及ぶところ」のことです。力ある人間によって支配され、苦しめられている人々に、人の支配ではなく、神の支配が実現するということをイエスは告げたのです。それは現実の不条理への挑戦でもありました。
人の支配と神の支配では、その目的も、大切にすることも異なります。一部の人間の欲望や野心による支配では、他の人々は持っているものを奪われ、生命を脅かされます。しかし、神の支配はそれとは異なる世界を創り出します。神の支配は、この世界が本来持っていた姿を取り戻します。神がこの世界を創られたのですから、人の支配によって失われたものを、神の支配は取り返すのです。
イエスはこの神の支配――神の国を宣べ伝えるために、ガリラヤの自然をたとえとしてたびたび語られました。ガリラヤに生きる動物や植物の姿を通して、神の国のことを伝えようとしたのです。そこには人の支配が及んでいなかったからかもしれません。神の国を知るために、人によって支配されていない自然の姿に目を向けることができるのかもしれません。
世界は分かち合うものだった
たとえば、森の中の木と木の関係に目を向けてみましょう。最近になって、木と木がお互いに支え合い、協力し合っていることが発見されました。『奇妙で不思議な樹木の世界』※1を見ながら、木と木の関係について、またそこから考えられる神の国のあり様について、考えてみましょう。
皆さんは森の木々はどのような関係にあると思いますか。私は、森の木々は互いに競争していて、より多くの日光を独占しようと急いで成長して、その競争に負けた木は枯れるしかない、と思っていました。
しかし実際には、木は他の木と一緒に森を作り、助け合うことで生き残りやすくなっているようです。木々が集まることによって、森の温度や湿度がちょうどいい具合に保たれ、冬は暖かく、夏は涼しくなります。木は隣の木にぶつかるまで枝を伸ばしますが、そうすることで枝と葉で屋根が作られ、嵐が来ても強風が入りこまなくなります。
さらには、木は他の木とつながり、栄養素や水分を分け合ったり、病気や干ばつの情報を伝えあったりしているそうです。木の根は菌根菌という菌類(キノコ)とつながっています。菌根菌は植物の成長に欠かせない窒素やリンなどを土の中から吸収して木に分けています。一方、木は光合成によって作った糖類などを菌根菌に分けています。
この菌根菌を通して、木は他の木にも栄養素や水分を分け合っていることがわかってきました。森の中には他の木を助ける大きな木があります。その大きな木は「マザーツリー」と呼ばれています。マザーツリーの周りには、発芽したばかりの小さな苗木が生えていることがあります。まだ小さな苗木にはあまり日光が当たらないため、十分な栄養素を作れません。するとマザーツリーが菌根菌を通して苗木に養分を分け、成長を助けてあげます。
一方、森にある切り株は、私たちの目には、もう死んだもののように見えますが、木は切り株になってもまだ生きています。しかし、枝も葉もないので、養分を作り出すことはできません。するとマザーツリーが古い切り株にも養分を分け与えます。そうすることで、切り株のままで何百年も生き続ける木もあるようです。
このように、森の木々は単に競争し合っているのではありません。森のすべての木々の状態がよいとき、それぞれの木々も守られ、成長しやすくなります。また、木は菌根菌と助け合っており、栄養を多く作り出せる木は、まだ幼い木や弱っている木と栄養を分かち合っています。
自然界は弱肉強食の世界だ、と言われることがあります。確かに一面を切り取ればそう見えるでしょう。しかし生き物は私たちが考えているよりもずっと助け合い、分かち合いながら生きています。それは木や菌類だけでなく、他のどんな生きものでもそうです。誰も自分だけでは生きられないし、独占しようとはしていない。世界とは分かち合うものとして創られていたのです。
神の国は終わらない
人間による支配が強まっていくときには、「世界は弱肉強食だ」といって、奪い、争い、独占しようとすることが正当化されるかもしれません。奪い、争い、独占することは、人が他の人に対して行うこともありますし、人が自然に対して――他の生き物に対して――行うこともあります。現在も森林破壊は急速に進んでおり、1分間で東京ドーム2つ分の森林が消えていると言われています。森の木々は分かち合っていたのに、人間はそこから奪い、独占しようとしている。
神の支配・神の国は、人間の支配とは異なるものです。この世界は分かち合うものとして創られていた。そうであれば、この世界を創られた神の行われる支配・神の国は、そこに生きる生命が恵みを分かち合うところであるはずです。イエスが語られたこと、行われたことも、助け合い、分かち合い、共に生きようとすることへと導こうとするものだったのではないでしょうか。
イエスを訴えた祭司長たち、あるいはイエスを十字架にかけたローマの権力者たちは、イエスが十字架で死ぬことによって、イエスが語り伝えたことも闇に葬り去ることができると考えていたことでしょう。しかし、神はイエスを復活させました。神の子イエスは墓の闇から出てきました。それはイエスが語り伝えたこと、神の国もまた、決して終わってはいないこと、人の支配が打ち破られ、神の支配が始まることを告げるのです。
この世のすべてを支配できると思いあがり、他者を支配し、また他の生き物を支配することは、人間の罪です。今も力ある人々は弱肉強食の論理を振りかざし、奪い、争い、独占しようとしています。けれども、この世界は分かち合うものとして創られていた。生き物は誰もが分かち合い、助け合い、共に生きるように創られていた。弱肉強食が自然だというのは誤解です。この世界は分かち合うもの。この世界に生きるすべてのものに分け与えられたものです。
分かち合い、助け合い、共に生きるときにこそ、生命は増え拡がり、豊かさが増していった。自然の一部である私たち人間も同じです。この世界を分かち合うときにこそ、私たちは真に豊かに生きることができるし、神の祝福がますます豊かに受けることができる。だから私たちは、復活の主イエスと共に、神の国を宣べ伝え、この世で表していくのです。
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
※1 『奇妙で不思議な樹木の世界』英国王立園芸協会監修、ジェン・グリーン文、クレア・マケルファトリック絵、加藤知道訳、創元社、2024年
参考文献 『イエス誕生の夜明け ガリラヤの歴史と人々』山口雅弘、日本キリスト教団出版局、2002年