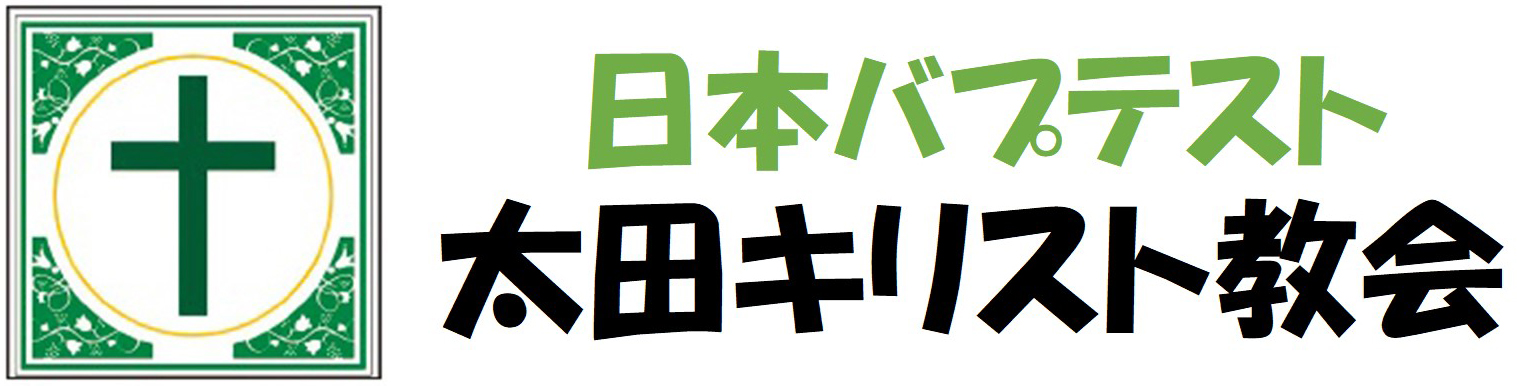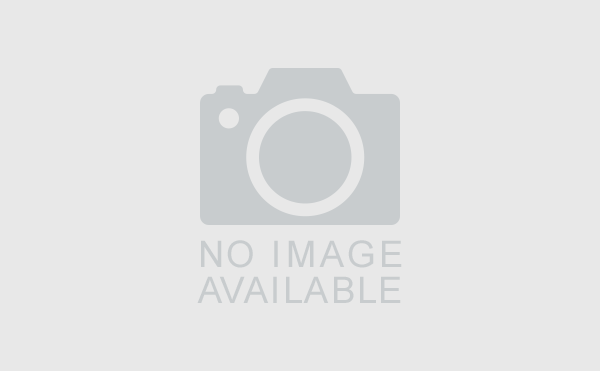礼拝メッセージ(2025年4月6日)「剣を取らずに、神に任せる」 マタイによる福音書26:47~56 杉山望牧師
力のない者たちを押しとどめる言葉
今日与えられた箇所は、イエスの受難を覚える箇所です。ガリラヤを出て、エルサレムに到着したイエスは、最後の晩餐を弟子たちと共にした後、ゲッセマネで悲しみ悶えながら祈られました。そこに十二弟子の一人であるユダが、武器をもった大勢の群衆を伴ってやってきます。ユダはイエスを祭司長たちに売り渡し、他の弟子たちも皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。それは衝撃的な事件です。
イエスを見捨てて逃げてしまう弟子たちは情けなく思えますが、弟子たちもイエスが捕らえられるのをただ黙って見ていたわけではありません。弟子の一人は剣を抜き、大祭司の手下の片耳を切り落としました。剣や棒を持った大勢の群衆を前にしながら、自分の身を危険に晒してでもイエスを敵の手から奪い返そうとした弟子がいたのです。
しかし、イエスは弟子たちを諭して、このように言われました。
『剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。』(マタイによる福音書26:52)
剣を取ることを押しとどめるイエスは、暴力的手段を用いない非暴力のモデルとして見られてきました。ただ今回、このイエスの言葉を聞いたとき、手段の良し悪しだけでなく、選んだ手段によってもたらされる結果のことにも心を向けているのではないかと思わされました。
「剣を取る者は皆、剣で滅びる」というイエスの言葉は、弟子たちに向けて語られたのであって、祭司長に遣わされた大勢の群衆に向けて語られたのではありません。大勢の群衆は、剣や棒を持ってきているのですが、そのような群衆には「剣で滅びる」とは警告せず、別のことを語られました。
11人の弟子たちに対して、大勢の群衆は圧倒的な力を持っています。力の差があればあるほど、より大きな力を持った者たちが暴力的な手段を使っても、それがすぐさま力ある者たちの滅びにつながるということは、なかなかありません。少なくとも、圧倒的な力を持った者たちは、剣を取ることで自分たちが滅びることなど、想像もできないでしょう。
でも、弟子たちにとっては、それは切迫した問題です。もし11人の弟子たちが剣を取り、大祭司の手下である大勢の群衆と戦ったならば、どのような結果になったでしょうか。全員が捕らえられたり、殺されたりして、イエスの弟子たちは完全に滅ぼされてしまったかもしれません。そのように弱く、危険に晒されている弟子たちに対して、イエスは「剣を取る者は皆、剣で滅びる」と語り、彼らが暴力的手段を用いることを押しとどめたのです。
英雄的な死よりも、イエスに従い続けること
振り返ると、エルサレムに上って行くまでに、イエスは三度、ご自身が引き渡され、殺されることを予告していました。その予告があったからか、弟子たちはゲッセマネにも剣を持ってきており、突然のイエスの逮捕という事態にも関わらず、その剣を抜いて大祭司の手下に打ちかかっていきました。最終的には逃げてしまった弟子たちの中にも、身を挺してイエスを守ろうと考えた人はいたのでしょう。
けれども、それはイエスが望んだことではありませんでした。剣を取ってはならない、というのは、暴力を選ばないという美徳というよりも、ここでは弟子たちが滅んでしまうことを避けさせるためのものだったのかもしれません。
小説や映画ならば、圧倒的な力を持つ敵に対して命がけで戦いを挑む人物が物語の主人公になります。現実でも、圧倒的な力に武器を持って立ち向かい、命を落とした人が英雄として崇めることがあります。しかしイエスは弟子たちが「英雄的な死」を遂げることを良しとはしませんでした。そもそも聖書には、犠牲の死を遂げることを英雄視する思想が見られないようにも思えます。
他方で、イエスは神に願って十二軍団以上の天使を送ってもらい、大祭司の手下を一掃する、ということもしません。そう願えば叶えられるけれども、イエスは大きな力で圧倒することを選びません。それはこの世で人間が犯す過ちの繰り返しとなってしまうからです。人間はより大きな力を求め、その力によって他者を支配しようとします。イエスはそんな世界に力を奪われた一人の人間として来られ、神の御心が実現される新しい世界の到来を宣べ伝えたのです。
人間の罪によって歪んだこの世界に神の国が到来し、新しい世界が創造されるために、イエスは神の御心に従い続けました。イエスはそのようなご自身のそばに弟子たちを置いておきたかった。イエスの姿を見、イエスの言葉を聞くことを通して、弟子たちが神の御心を知ることができるように願っていました。そのためには、弟子たちは滅んではいけない。英雄的な死などもってのほかです。剣を取って滅びるくらいなら、イエスを見捨てて逃げてしまう方が、まだましだったのかもしれません。
弟子たちに期待されていたのは、最後までイエスに従い続け、その姿を見、その言葉を聞き続けることでした。イエスのことを三度知らないと言ってしまったペトロでも、大祭司の屋敷の中庭までは従っていました。そして、イエスが十字架で死なれ、墓に葬られるまで従い続けた人もいました。マグダラのマリアともう一人のマリアです。この二人が最初に天使からイエスの復活を告げられることになります。
剣を納め、神に任せる
「剣をさやに納めなさい」、というイエスの言葉は、ゲッセマネで祈られた言葉とつながっているように思えます。
『父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの願いどおりではなく、御心のままに。』(マタイによる福音書26:39)
剣を取る、ということは、武器を使うとか、暴力に頼るということでもあり、さらに広げて解釈すれば、様々な人間的な力を使って、自分の思い通りにしようとすることだと考えることもできます。剣は、自分の願いの実現を邪魔するものを攻撃し、排除するためのものなのかもしれません。そのようなことは、誰だって多かれ少なかれ行っているでしょう。
しかし、イエスは剣を取らなかった。受難の時が目前に迫っていることがわかっていて、死ぬばかりに悲しく、悶えて苦しんでいた。できることなら、その苦しみを過ぎ去らせてほしかった。心の底からそう願っていた。それでもイエスは、「わたしの願いどおりではなく、御心のままに」と祈ったのです。そして、祈っただけでなく、ご自身は最後まで剣を取ることなく、神の御心に身を任せました。それが神の子イエス・キリストなのです。
「剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。」
イエスは私たちが滅びの道を選ばないことを願っています。イエスに従っていくこと、いつでもそばにいて、イエスの姿を見、イエスの言葉を聞くことが願われています。イエスはご自身のすべてを神に委ねました。そこには、神がこの世に介入し、御心を行ってくださる、という信頼がありました。この世で力を持つ者たちが何をしていようとも、最後に勝利するのは神である、という信仰があったのです。
私たちはイエスの姿とイエスの言葉を通して、神への信仰を学びます。イエスは私たちにも、「剣を納めなさい」と語っておられるでしょう。そしてイエスと共に、「わたしの願いどおりではなく、御心のままに」と祈るように招かれています。ただその祈りは、時には祈ることがとても難しく感じるでしょう。イエスでさえ、悲しみもだえながら祈られたのですから。
剣を納めるために――自分の力に頼るのではなく、神に信頼するために――、私たちはゲッセマネのイエスに目を注ぎます。そして、イエスと共に祈らせてもらいます。いや、私たちの祈りを、イエスが共に祈ってくださっているのかもしれません。私たちの思いを超えて、私たちを救い、この世に神の国をもたらそうとしておられる神の御心に、少しずつでも信頼を重ねていきたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988