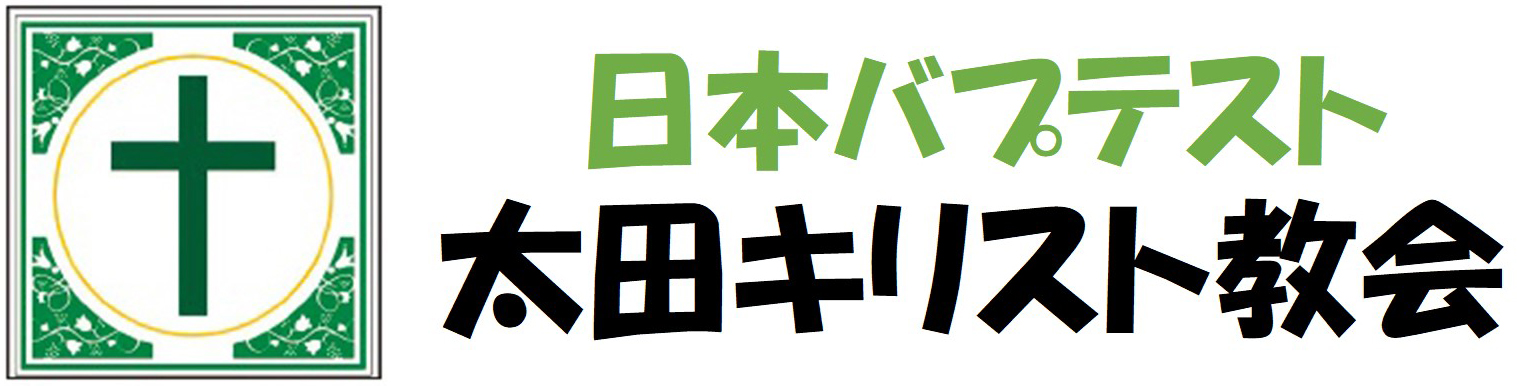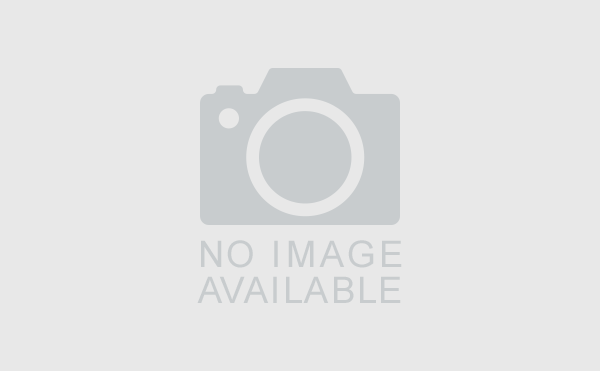礼拝メッセージ(2025年5月11日)「信仰は一つでも教会はいろいろ」ガラテヤの信徒への手紙2:15~3:6
信仰義認論
先週、バチカンで次のローマ教皇を選ぶ選挙「コンクラーベ」が行われました。「コンクラーベ」とは、ラテン語の「ともに」という言葉と「鍵」という言葉を一つにした言葉だそうです。教皇の選挙権をもつ枢機卿が集まり、誰かが投票総数の3分の2以上の得票を得るまで、何度も繰り返し投票が行われます。その間、枢機卿たちは宮殿に閉じ込められ、外部との接触は一切立たれます。教皇不在の期間を長引かせないために行われるようになったコンクラーベは、決まるまで繰り返されるので「根競べだ」と冗談を言われることもあります。
今回は4回目の投票で選ばれたプレポスト枢機卿は、アメリカ出身の初の教皇となりました。教皇名は「レオ14世」で、南米のペルーで約20年間を過ごしてきたこともあり、ラテンアメリカからの支持が大きかったようです。レオ教皇は就任の演説で、「私たちは共に歩み、常に平和を求め、特に苦しむ人々に寄り添う教会でありたい。この新しい使命のため、全教会と世界の平和のために祈ろう」と呼びかけました。
カトリック教会でも、欧米では教会離れが進んでいたり、司祭や修道士、神学生が減ったりしているそうですが、それでも世界で約14億人の信徒を抱えています。教皇には大きな影響力があると思いますので、ぜひ苦しむ人々の声を聴き、寄り添い、平和を求めて歩んでほしいと願います。
私たちバプテスト教会はプロテスタントの一派ですが、プロテスタントがカトリックから離れたのは今から500年ほど前の宗教改革のときです。宗教改革の中心人物であったルターが訴えたことの一つは「信仰義認論」でした。
今日のテキストであるガラテヤ書2章は、ルターの信仰義認論に大きな影響を与えた箇所です。それは、「人は自分の行いによって義とされる――救われる――のではなくて、信仰によってのみ義とされる――救われる――」ということです。人間の行いに応じて神の救いが与えられるのではなくて、イエス・キリストによってのみ救われるのだ、ということをルターは訴えました。
ユダヤ人を異邦人から区別する律法
パウロは、「人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる」、「律法の実行によっては、だれ一人として義とされない」と言っています(ガラテヤ書2:16)。パウロが信仰と対比させたのは、一般的な意味での「行い」ではなく、「律法の行い」でした。このパウロの主張の背景には、ガラテヤ書2章11節から14節で書かれている出来事がありました。
ガラテヤ教会は異邦人の多い教会でした。一方、ユダヤ人は異邦人と食事を共にすることを律法によって禁じられていました。それでも、パウロだけでなくペトロやバルナバもガラテヤ教会の人々と一緒に食事をしていました。以前ペトロは、「神は人を分け隔てなさらないことが、よく分かりました。どんな国の人でも、神を畏れて正しいことを行う人は、神に受け入れられるのです」と言っていました(使徒言行録10章34~35節)。その言葉の通り、救いはユダヤ人だけのものではなく、誰もが受けることができるものだと、ペトロもパウロと同じように考えていました。
ところが、ガラテヤの教会にエルサレム教会の代表であるヤコブの下からある人々が遣わされてきました。するとその後から、ペトロは教会の異邦人と一緒に食事をすることを避けるようになりました。急に態度を変えてしまったペトロにパウロは憤りました。ペトロの態度は、ユダヤ人と異邦人を分け隔てるものであったからです。
他の箇所でも、パウロは異邦人クリスチャンにも割礼を受けさせようとするユダヤ人宣教者と論争をしています。そのようなことを踏まえると、パウロが問題とした「律法の行い」とは、ユダヤ人を異邦人から区別しようとすることだと考えられます。そこでは、神の救いに預かるためにはユダヤ人にならなければならないので、ユダヤ人を異邦人から区別する役割を持った律法、すなわち「割礼」と「安息日規定」、そして「食事規定」を守らなければならないことになるのです。
そのような律法を守ることは、異なる文化・社会の中で生きる人びとにとっては重荷となります。それはユダヤ人にとっては異なる文化・宗教に囲まれた中で、神の民としての一致と信仰を保つための重要なものでありました。しかし、救いがユダヤ人だけに限定されたものではなくなったときには、人を区別する律法は必要なものではなくなりました。人は神の恵みによって義とされるのであって、律法によって義とされるのではないからです。
エルサレム教会のようにならなくても
エルサレム教会のユダヤ人クリスチャンは、なぜ割礼や食事規定といった律法を守り続けていたのでしょうか。その背景には、彼ら・彼女らが置かれていた難しい状況があったようです。エルサレムはユダヤ教の中心地です。そこには神殿があり、祭司長など宗教指導者も多くいました。
新しく誕生したばかりの教会は、まだユダヤ教の一派として見なされていました。エルサレム教会がユダヤ人の中で信頼を得て活動していくためには、教会の人々も律法を守ることが必要でした。教会の指導者であった主イエスの兄弟であるヤコブは、ファリサイ派の人々からも尊敬を受けるほどに、律法を真剣に守っていました。
ガラテヤの教会には多くの異邦人がいました。エルサレム教会の人々もガラテヤ教会の人々も同じ主イエスを信じていました。しかし、律法の食事規定を守っていない異邦人信徒と一緒に食事をすることは、ユダヤ人の社会に置かれたエルサレム教会にとって大きなリスクを伴いました。食事規定の律法を破ることは、ユダヤ人の反感を買って、共同体から排除されることになりかねないからです。
ヤコブがペトロのもとへ人を遣わしたのも、その後、ペトロが異邦人と食事をすることを避けるようになったのも、エルサレム教会の存続を心配したからかもしれません。そのことはパウロもわかっていたはずです。なぜなら、パウロ自身が「徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとして」いたし、「先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心」だったからです(ガラテヤ書1章13,14節)。
だからでしょうか、パウロはエルサレム教会がガラテヤの教会のようになることを求めてはいません。ユダヤ人クリスチャンが律法を捨てて、異邦人のようになりなさい、と言いたいのではないのでしょう。パウロが訴えたことは、ガラテヤの教会がエルサレム教会のようになることを求めないこと。異邦人クリスチャンがユダヤ人のように律法を守らなければならないということはない。主イエスの恵みによって救われる、ということには、ユダヤ人も異邦人も関係ない、ということだったのでしょう。
いろいろな教会が共有していた救いの出来事
私はこれまで、パウロの宣教活動や手紙に現れてきた異邦人とユダヤ人との衝突という出来事を、異邦人の立場から見ていました。私はユダヤ人ではないので、自然と異邦人の立場から見ていました。ユダヤ人クリスチャンは新しい歴史が始まったのに、古い掟に捕らわれている、と思っていました。
でも今回、エルサレム教会がユダヤ人の間でどのような状況に置かれていたのか、ということを想像してみると、エルサレム教会のユダヤ人クリスチャンの葛藤や悩みに共感できました。まだ歴史の浅い教会が、圧倒的少数者である社会の中で、どのように周囲の人々との関係を作っていくことができるのか。それは日本社会の中の教会・クリスチャンにとっても、身近な事柄なのではないでしょうか。
現実として、私たちが生きているのはキリスト教社会ではありません。クリスチャンは圧倒的な少数者である環境で暮らしています。だから、キリスト教社会の中のクリスチャンのように、他の文化や宗教とは切り離された生活ができるわけではありません。関わりをもち、折り合いをつける場面が出てくる。でも、それは最初に誕生したエルサレム教会も経験したことだったのです。
だから、教会のあり方はいろいろあって当たり前なのでしょう。その教会の置かれた場所によって、あるいは時代によっても、教会の形は変わっていくものです。それでも、共有するものはある。エルサレム教会とガラテヤの教会の人々は異なる生活を送っていましたが、イエス・キリストの恵みによって救われた、という経験は共有していたのです。
「キリストは、わたしたちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世からわたしたちを救い出そうとして、御自身をわたしたちの罪のために献げてくださったのです。」(ガラテヤの信徒への手紙1:4)
「生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わたしのために身を献げられた神の子に対する信仰によるものです。」(ガラテヤの信徒への手紙2:20)
神から離れていた私たちのために、イエス・キリストはご自身を献げてくださった。神は私たちを見捨てることなく、神の子を遣わしてくださり、救いの手を差し伸べてくださった。私たちがどこにいようとも、何をしていようとも、どんな思いでいようとも、主イエス・キリストは私たちと共にいてくださる。私たちが負わされたどんな苦しみも、主は共に担い、背負い、助け出してくださる。その主イエスの救いへの信頼を、私たちもしっかりと握りしめて歩んでいきましょう。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考文献 『ユダヤ人も異邦人もなく パウロ研究の新潮流』山口希生、新教出版社、2023年