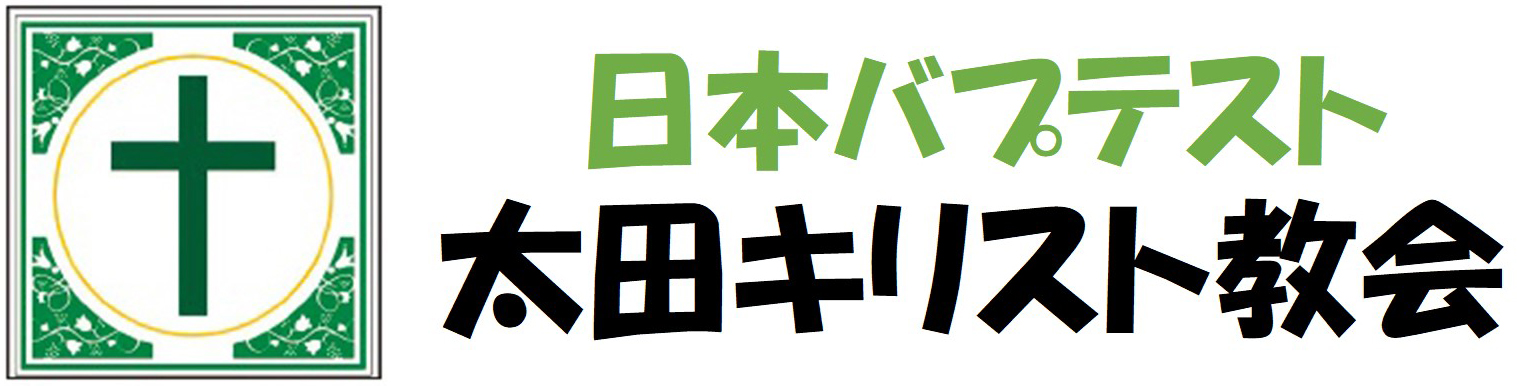礼拝メッセージ(2025年7月13日)「足るを知らない世界」民数記11:1~15

不平不満に応えてくださる方
先週は民数記から理想的な神の民の姿を見ました。そこでは人々が主の命令に従って旅立ったり、留まったりしており、神への信頼が表されていました。今日の箇所では一転して、人々は神に対して激しく不満を言い出しています。
神に不満を言う、ということが、無礼で傲慢な態度だと思われるかもしれません。でも、聖書を読んでいると、神に不満を言ったり、あるいは心身が満たされないことを訴えたりすることは、たびたび目にします。
民数記の前、出エジプト記にも、人々の不満は何度も訴えられます。その中でも今日の箇所と関連が深いのは、出エジプト記16章のマナの出来事です。そこではエジプトを脱出して荒れ野を旅していた人々が空腹のためにモーセとアロンに不平を言っています。
「我々はエジプトの国で、主の手にかかって死んだ方がましだった。あのときは肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全会衆を飢え死にさせようとしている。」(出エジプト記16章3節)
この訴えに対して神は怒っておられません。その不平を聞いて受け止め、毎日必要な分の食料を与えることにされたのです。それは天から降って地に積もるパンであるマナと、空から飛んでくるうずらでした。
200万人という大所帯で荒れ野を旅していた人々にとって、食料問題は命に関わる深刻な問題でした。自分たちでは食料問題を解決する手段がありませんので、人々は荒れ野に導かれた神に不平を述べたのでしょう。神に対して不平不満を言うということはいけないことのように思ってしまいますが、その不平不満がもっともなものだったので、神はその要求に応えて必要を満たし、命を守られました。
必要が満たされなければ、誰でも不平不満を抱くものです。赤ちゃんの頃は、誰もが泣いて訴えていました。年を重ねるにつれて、伝え方が変わったり、我慢したりすることも増えていきます。それは大切なことですが、神は私たちの不平不満がもっともなものであるとき、その訴え方がどのようなものであっても、その思いを受け止めて、必要を満たしてくださる方なのです。
貪欲さが引き起こした災い
しかし、今日の箇所に目を向けると、人々の不満を聞いた主である神は、憤っておられます。神を憤らせた人々の不満は、このようなものでした。
「誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をただで食べていたし、きゅうりやメロン、葱(ねぎ)や玉葱(たまねぎ)やにんにくが忘れられない。今では、わたしたちの唾(つば)は干上がり、どこを見回してもマナばかりで、何もない。」(民数記11章4~5節)
「どこを見回してもマナばかり」だと言っているように、荒れ野を旅する人々には、既にマナが与えられていました。マナはどこに行っても必ず毎朝与えられました。それは荒れ野で生き抜くために神が与えてくださった奇跡の食べ物でした。初めはそれに驚きつつ、感謝して受け取っていたはずですが、ここでは感謝の思いは全く感じられません。人々はエジプトで食べていた豊かな食材と比べて、神が与えてくださる食べ物に不満を述べたのです。
ちなみに、マナは荒れ野限定の食べ物で、人々が約束の地に到着した後はその土地の食べ物を食べるので、マナは天から降らなくなります。確かに荒れ野ではエジプトのように豊かな食材ではありませんが、マナは荒れ野を旅する間、命をつなぐための必要を満たす食べ物でした。それでも、もっと良い物を、もっとたくさん求める人々は、それに不満をもってしまったようです。
このような不満に対して、神は一か月もの間、食べ続けることができる量の肉を与えました。海から飛んできた大量のうずらが宿営の周りを埋め尽くしました。地面から90㎝の厚さになるほどのうずらが、地の果てまで埋め尽くしました。人々は肉が食べられると喜んで、二日間にわたって集め続けました。その量は、一番少ない人でも2000ℓを超えていたほどです。
ところが、人々がその肉を食べ始めると、肉がまだ歯の間にあるうちに、激しい疫病が広まりました。そのために、その場所はキブロト・ハタアワ(貪欲の墓)と呼ばれるようになりました。(民数記11章31~34節)
マナは毎日、その日の分だけを集めていました。次の日にも神がマナを与えてくださるという信頼と、神がいつも必要を満たしてくださるという感謝がそこにはありました。ところがその信頼と感謝を失った人々は、神の賜物に不満を言い、食べきれないほどの肉――必要以上の肉――を一度に集め、災いを引き起こしてしまいました。これは人々の貪欲さが引き起こした災いの一例です。
足るを知らない世界
人々の欲望が大きくなっていくと、災いを引き起こすことがあります。私たちにとって問題なのは、現代の資本主義社会が欲望を刺激して、拡大させるという性質をもっていることです。資本主義は無限の成長を前提としており、経済成長が永遠に続くことを求めます。経済成長のためには、より多くの物が消費され、より多くのエネルギーが使われることが必要となります。
しかし、人間にとって必要な物も、生きるために必要なエネルギーも限りがあります。そこで資本主義では、必要を満たすことではなく、欲望を刺激して、消費を促します。そのための装置の一つが「広告」で、「もっと便利に」とか、「もっと幸せに」といった感情に訴えて、欲望を無限に生じさせようとします。それに伴って、エネルギーの消費量は20世紀に入ってから爆発的に増えてきました。二酸化炭素などの温室効果ガスも増え続け、地球温暖化が引き起こされています。
地球温暖化の影響は、異常な猛暑や豪雨など、私たちも日常的に感じています。世界各地でも前例のない災害が頻発しており、アメリカでも先日、洪水によって多くの人の命が奪われました。本当に痛ましい災害ですが、気候変動による犠牲者は発展途上国の方がはるかに多くなっています。過去50年間で見ると、気候変動に関連した災害や異常気象の死者のうち91%が発展途上国の人々だったといいます。
聖書に記された災いも、地球温暖化による災害も、人々の欲望が関連していますが、まったく同じものではありません。今日の箇所の災いは自らの貪欲さが引き起こしたものでしたが、地球温暖化は、その原因にほとんど関わりのない人々の方が圧倒的に多く犠牲になっています。だから、今も進んでいる地球温暖化に関連した災害を、神の裁きと言うことはできない、と私は考えています。
ただ、欲望や貪欲さが問題となっていることは共通しています。資本主義社会は、格差の拡大も引き起こしています。その傾向はどんどん強まっていて、災害や異常気象が頻発し、新型コロナウイルスのような伝染病も蔓延する中でも、超富裕層の人々は資産を増やし続けています。2021年の時点では、世界の上位1%の超富裕層の人々が世界全体の資産の37.8%を独占していました。それでもなお、資産を増やそうとすることは止まりません。
古代中国の老子の言葉に、「足るを知る」というものがあります。「現在の自分の状況に満足する、今目の前にあるものに対して感謝する」という意味の言葉です。それは、神からいただいたマナに感謝していた人々の姿と重なります。現在は「足るを知らない世界」です。より正確には、「満ち足りることを許さず、いつも飢え渇き、無限に求めさせる世界」です。それは人々を貪欲にさせる世界であり、神を忘れた世界です。
必要が満たされる世界へ
「足るを知る」といっても、それは自分の置かれた現状を諦めるとか、不平不満を言わずに我慢する、ということではありません。聖書の人々が不満を訴えたように、自分にとって必要なことは求めるべきですし、神はそれを満たすことを望んでおられます。
今の世界を生きる私たちにとって、「足るを知る」とは、一つには資本主義社会の中で拡大していく欲望から解放されることでしょう。満足することを良しとはされず、絶えず欲望を持つこと――常に不満であること――を押しつけられていては、心や魂が飢え渇いてしまいます。人は今の社会が訴えるほど、多くの物がなくても幸せに、満たされて生きることができるのではないでしょうか。
それと共に、あるいはそれ以上に、今大切な「足るを知る」ということは、今の社会が「足るを知る」ことを良しとするものに作り変えられることでしょう。無限に成長することはできませんし、その限界や弊害が現れてきています。成長を目的とするのではなく、必要を満たすことを目的とする方向へと向きを変えていくことが望ましいのではないでしょうか。
この世界がそのように変えられていくならば、物やエネルギーの消費も減っていくでしょうし、長時間労働を強いられたり、不安定な職に追い込まれたりすることもなくなっていくかもしれません。時間の使い方も変わって、本当に大切にしたいことに時間を使うことができるようになっていく。神と人、人と人、人と被造物との関係も、もっと良い関係に、本来のあるべき形に近いものに変わっていくと思うのです。
成長することは良いことです。でも、無限の成長など必要ありません。私たちは子どもの成長を願いますが、だからといって身長が3mや4mになることを願いません。無限の成長はあり得ないし、必要でもありません。
神は私たちの必要を満たしてくださいますし、満たすことができる世界を既に与えてくださっていました。足ることを知らない世界では、与えられている物への感謝を失い、貪欲に物を求め、災いを引き起こしてしまいます。足ることを知る。心身の必要が満たされ、生かされることに信頼と感謝をもち、神と共に、隣人と共に、他の被造物とも共に生きていく。そんな世界に新しく創造されていくことを願い求めたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
『資本主義の次に来る世界』ジェイソン・ヒッケル、東洋経済、2023
『資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか』ナンシー・フレイザー、ちくま新書、2023
※Graham lightによるPixabayからの画像