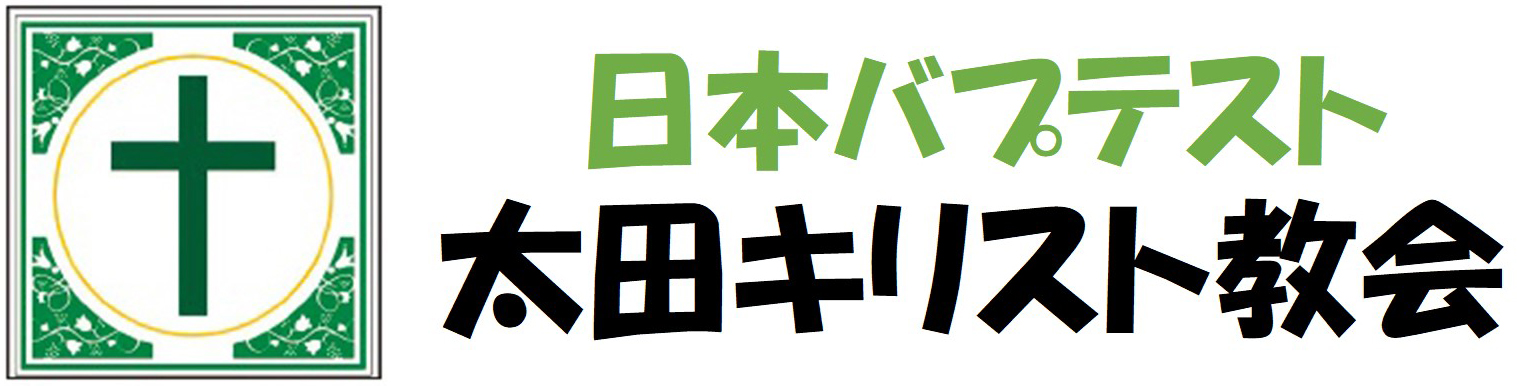礼拝メッセージ(2025年7月20日)「貧しさのない公平な社会へ」民数記13章1~3節、17~29節

聖書を利用して暴力を正当化しない
旧約聖書には、戦争や侵略、虐殺といった暴力的な出来事がいくつも含まれています。その中には歴史的に起こった出来事もあれば、何かしらのメッセージを伝えるためにまとめられた物語もあるでしょう。いずれにしても、そのような暴力が、愛の神の言葉を伝える聖書に含まれている、ということに戸惑いを感じることもあるでしょう。
今日の箇所では、約束の地であるカナンの南端に到着したイスラエルの民が、12部族の代表者を遣わして、カナンの土地や住民の偵察を行っています。その土地の豊かさだけでなく、住民の強さや人数、町の様子や城壁があるかどうかなどを調べているので、この偵察が軍事的な侵略の準備であることが伝わってきます。そしてこれ以降、イスラエルの民はいくつもの民族と戦い、時には相手を絶滅させたという記事が書かれています。
暴力を含むこのような個所を読むときに避けるべきことは、聖書を利用して暴力を正当化することです。特に現在のイスラエル国家は、聖書を根拠としてパレスチナの地に「ユダヤ人だけの国家」を作ることを正当化しています。しかしそれは、聖書のメッセージを歪めており、神の御心に反するものだと私は考えています。
理由の一つは、「ユダヤ人だけの国家」という発想が聖書的ではないことです。先週読んだ民数記11章には、イスラエルの民に「雑多な他国人」(民数記11章4節)が加わっていたことが書かれていました。イスラエルの民がカナンに定住してからも、その土地から他民族が全くいなくなったとは読み取れません。そして何より、神は律法を通してイスラエルに「寄留者を愛すること」を命じていますし、イスラエルに与えられた主の祝福はすべての人に届けられるものとして託されたものです。外国人や他民族を排除して、同じ民族だけのための国を作るという発想が、神の御心に適うものであるとは到底思えません。
また、申命記28章には、神の祝福と呪いについて語られています。イスラエルの民が「主の御声によく聞き従い」、主が「命じる戒めをことごとく忠実に守るならば」祝福を受け継ぐことができますが、そうでなければ呪いが臨み、祝福を失うとされています。ところが、現代のイスラエル国家は世俗化が進んでいます。中には超正統派のように、厳格に律法を守るグループもいますが、国民の半数近くはユダヤ教の教義も戒律もほとんど守らずに生活しています。政治的・軍事的な判断においても、神の御心を尋ね求めたり、律法に従おうとしたりしている様子はうかがえません。そのような世俗化した国家が、自己正当化するときだけ聖書を根拠とすることは、神への冒涜とさえ感じます。
パレスチナに国家を建設することについては、ユダヤ教の超正統派から神の意志に反することだという批判がなされています。イスラエルの建国の背景には、欧米諸国が中東で影響力を持つための拠点として利用するという目的もありました。キリスト教会の中にもイスラエルを支持しているグループがありますが、人間の都合で作られた世俗的国家であるイスラエルが行っている暴力を、聖書によって正当化することはできない、と私は考えます。聖書には暴力的な内容が含まれていますが、大小を問わず、聖書を利用して暴力を正当化することはしないように気をつけたいと思います。
貧しい人がいない社会を作ることが目的
今日はこの箇所を、出エジプトの物語全体の流れや、その旅の目的という観点から考えてみたいと思います。約束の地カナンの偵察という出来事も、奴隷とされていたエジプトを脱出して、約束の地カナン導かれる旅の一部だからです。申命記では、出エジプトという出来事について、このように告白されています。
「わたしたちの先祖は、滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに寄留しました。しかしそこで、強くて数の多い、大いなる国民になりました。エジプト人はこのわたしたちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。わたしたちが先祖の神、主に助けを求めると、主はわたしたちの声を聞き、わたしたちの受けた苦しみと労苦と虐げを御覧になり、力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきこととしるしと奇跡をもってわたしたちをエジプトから導き出し、この所に導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。」(申命記26章5~10節)
虐げられ、苦しめられ、重労働を課されていた人々を、そこから導き出し、新たに豊かな土地を与えた、というのが出エジプトの出来事です。ここではっきり語られているのは、エジプトでの苦難は人為的なものであった、ということです。ファラオを頂点とした支配体制の下で、奴隷とされた人々は社会から疎外され、搾取され、貧しくされていました。それは偶然の出来事ではなく、まして自己責任として当然受け止めるべきものでもありません。神の意志に反して人々を虐げる支配者がいたのです。
そこで神がなされたことは、エジプトの支配体制の中で、イスラエルの民を支援することではありませんでした。貧しくされる人々を生み出す社会の中から導き出すことを、神は実現されました。そこから導き出すからには、約束の地で神の御心に沿って新しく作られる社会は、エジプトとは異なるものにならなければなりません。
約束の地は、「乳と蜜の流れる土地」と呼ばれます。それは多くの収穫が得られる土地の豊かさを表していますが、一方でエジプトも様々な食材が手に入り、文明を発展させることができる豊かさを持っていました。神が導かれる新しい社会と、奴隷を酷使していたエジプトとの違いは、土地の豊かさとは別のものだったのではないでしょうか。
「あなたの神、主は、あなたに嗣業として与える土地において、必ずあなたを祝福されるから、貧しい者はいなくなるが、そのために、あなたはあなたの神、主の御声に必ず聞き従い、今日あなたに命じるこの戒めをすべて忠実に守りなさい。……あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。」(申命記15章4~5節、7~8節)
律法は、貧しい人がいなくなるために与えられたのです。土地が豊かであっても、その豊かさが一部の人に独占され、多くの人が奴隷のように貧しくされるのであれば、エジプトから脱出した意味は失われます。約束の地へ偵察に出た時に、またその報告を聞いたときに、イスラエルの民は旅の目的を理解していたのでしょうか。その土地の豊かさを知った時、それを分かち合うことを思い浮かべたのでしょうか。自分たちだけで独占したり、一部の人間がその利益をむさぼったりするイメージでいたとしたら、神の目指す旅の目的からは離れていたと言わざるを得ません。
出エジプトの目的は豊かさを独占することや、他民族を征服し、排除することではありません。神が定めた目的は、イスラエルの民が豊かさを分かち合う新しい社会を作ることです。私たちがこの出来事から学ぶべきことは、豊かさを奪うことを正当化することではなくて、どのような困難があっても、豊かさを分かち合い、貧しい人がいない社会が作られることこそ、神の御心である、ということなのではないでしょうか。
希望の物語
出エジプトの出来事を通して示された神の御心は、過去も、現在も、そして未来も変わることのないものでしょう。その一方で、旧約の民がエジプトで奴隷とされていたように、現在も多くの人を虐げ、苦しめ、重労働を課すような社会が作られています。
神がイスラエルの民にカナンの地を与えたように、私たち人類に与えられた地球はとても豊かな世界でした。たくさんの資源があり、多くの生き物によって生命が育まれ、安定した気候のもとで文明を発展させることができました。その豊かさを分かち合うことができれば、貧しい人のいない世界を作ることもできたでしょうし、人間以外の生き物との共存することもできたでしょう。
しかし今の人類社会は、世界規模で地球の豊かさをむさぼり、その利益は一握りの人が独占してしまうものとなっています。格差はとてつもない規模に広がり、何億人もの人が貧困に苦しみ、日本でも重労働を課されたり、生活が苦しくなったりする人が増えています。それも権力を握った人たちが意図的に作り出してきた社会の構造です。そのような意味では、私たちも旧約のエジプトのような社会の中に捕らわれているのかもしれません。
そこから脱出することは、人間の力ではなし得ないものでしょう。しかし、出エジプトを導かれた主は、新しい世界を創り出すことのできます。主なる神が今も昔も変わらない方であるなら、今も主は貧しい人のいない世界、豊かさを分かち合うことのできる社会を創るように呼びかけ、招き、導いておられるでしょう。
豊かさが独占される不公平な社会では、互いへの信頼感も連帯感も失われます。健康状態は悪化し、犯罪率も増加し、欲求不満は高まり、不安感が広がります。それに加えて、現在の社会は気候変動による異常気象や前例のないような災害も引き起こし、命の危機や生活基盤の崩壊をも生み出しています。
幸福度を高めるためには、分かち合うことが個人レベルでも、社会や国家のレベルでも当たり前になっていく方が確実でしょう。それはしっかりとした福祉制度を創ったり、誰もが必要なサービスを利用できるようにしたり、基本的なニーズを満たすことを保証したりする。互いの重荷を担い合い、共に生きていく。そうなれば、ゆとりをもって人生を楽しみ、隣人ともつながりをもって生きることができるでしょう。そしてそれこそ、神に作られた人間の本来の姿なのではないでしょうか。
神が導くのは貧しさのない公平な社会です。現在の社会のあり様とは程遠いかもしれませが、神が苦しむ人々の叫びに応えて新しい社会へと導かれる方である、という希望の物語を、聖書から語り継いでいきたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
『反貧困の神 旧約聖書神学入門』ノルベルト・ローフィンク、キリスト新聞社、2010年
『資本主義の次に来る世界』ジェイソン・ヒッケル、東洋経済新報社、2023年