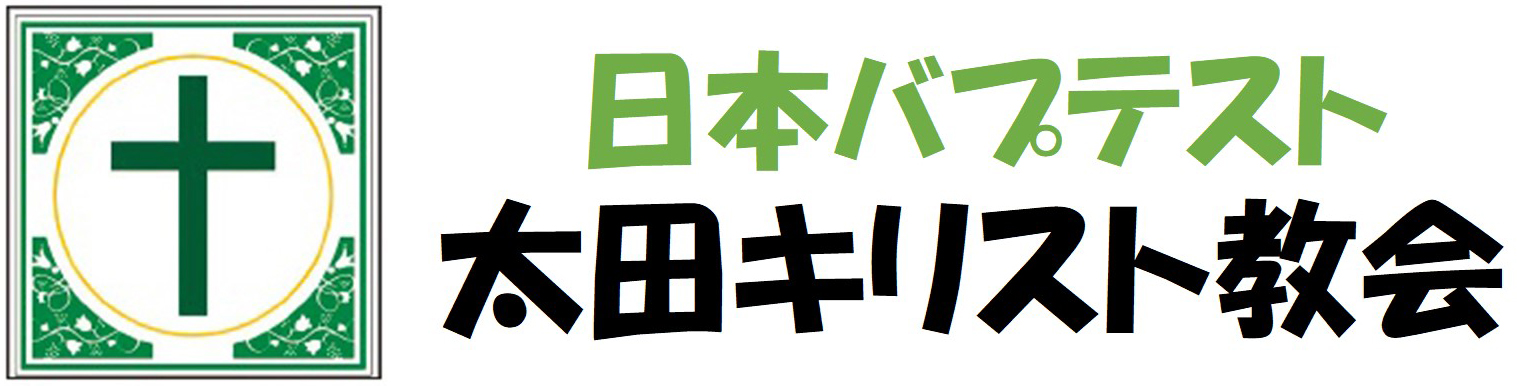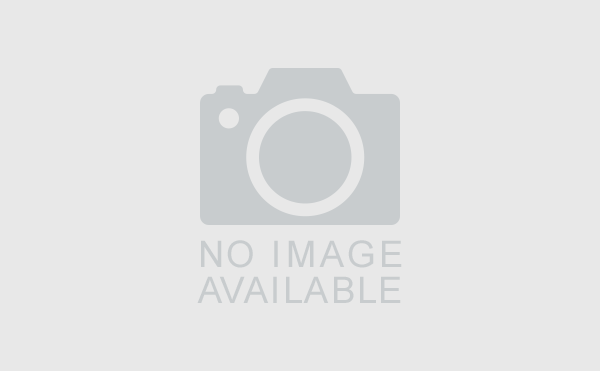礼拝メッセージ(2025年7月6日)「理想に目を向けて」民数記9:15~23

講演会の分かち合い
昨日、北関東地方連合の伝道委員会と教会教育委員会の共催で、『今こそ考えよう、教会の伝道と教会教育』という題の講演会が行われました。教会教育の研究をライフワークとしておられる小見のぞみ先生がお話してくださって、色んな気づきを与えられるときとなりました。
たとえば、プロテスタント教会では言葉で理解することや頭で考えることが中心になりがちですが、信仰は体で経験したり、心で感じたりすることも大切だそうです。それはたとえば赤ちゃんは言葉が話せなくても、体で安心できる場所を感じることができるように、教会が皮膚感覚で安心できる場所だと感じられるからこそ、信仰はその先に進んで行くことができる、ということだそうです。
体で経験する信仰としては、毎週の礼拝を一緒にささげることもそうですし、バプテスト教会にとっては全身を水に沈めるバプテスマも特徴的な体験だと話しておられて、なるほど、と思いました。頭で考え、理解しようとすることももちろん大切ですが、体や心で感じることも、教会が大切にすべきことなのでしょう。今日、行われる主の晩餐式も、一緒にパンとぶどう酒を飲むという体験をするものです。バプテスマと主の晩餐という二つの礼典は、イエス様に教えられたこととして大切なだけでなく、私たちの信仰のためにも大切なものとして教えてくださったのかもしれません。
もう一つ、共感したことは、キリスト教教育は人間を作り直す(reform)働きではなくて、神の子として形作る(form)働きである、ということです。失敗作を作り直すようなものではなくて、まだ完成していないものを一緒に形作っていくことかと受け止めました。それは神がこの世界を創造し続けておられる働きにも似ていると思います。
私たちは誰もが神によって形づくられ、神の目に高価で尊い存在とされました。私たちはそれぞれの人生の中で何度も変化し続けますし、完成に至るときはありません。私たちを愛してくださっている主なる神が、私たちに手を触れ、聖霊を注ぎ、私たちを形づくってくださる。その神の御業に教会も加わらせていただいていると言えるのではないでしょうか。
収奪の歴史と憲法の理想
最近、私が気になっていることの一つは、排外主義が目立っていることです。ヨーロッパやアメリカで広がってきた排外主義や人種差別が、日本でも公然と現れるようになったことに恐れを感じています。
言葉や文化が異なる人と暮らそうとすれば、トラブルが生じるのは当たり前です。ただ、それと生活の苦しさは関係ありません。現在、多くの世界が資本主義社会となっていますが、資本主義社会では資本の蓄積が目的とされ、一握りの人々が資本を独占し、他の国民から搾取して富を増やしてきました。一方、国民としての権利を持たない人に対してはもっと暴力的に収奪を行ってきました。奴隷や植民地の住民が収奪の対象でした。しかし人種差別を行い、人権を認めず、収奪を行うことは今も続いています。
今年はアジア・太平洋戦争の敗戦から80年を迎えます。日本はヨーロッパの列強諸国にならって、他国を侵略・支配し、収奪を行ってきました。戦争で負けたことによって、沖縄と北海道以外の植民地は失いましたが、他の国や人々から奪うことは、欧米諸国と共に続けてきたのではないでしょうか。
戦後、新たな憲法が作られました。その憲法の前文では、他の国の人々を信頼し、協力して平和を維持していくこと、自分の国のことだけでなく、他の国のことも考え、対等な関係に立つことを謡っています。戦後の日本は過去の過ちを反省しながら、世界の人々と共に平和に生きるという理想に目を向けたのです。
神の民の理想の姿
民数記が現在の形でまとめられたのは、バビロニア捕囚から解放された後だと考えられています。それはイスラエルの民にとって、国家の滅亡と神殿の破壊という挫折の経験から立ち上がって、新たに歩みだそうとする時でした。そこでまとめられた民数記では、先祖の過ちを記憶しつつ、神の民としての理想に目を向けようとしています。
今日の箇所は、神の民としてまさに理想的な姿を表しています。イスラエルの民は、シナイ山でモーセが律法を再度受け取った後、いよいよ約束の地を目指して旅立とうとしていました。民数記1章の人口調査によれば、成人男性だけで60万人以上。女性や子どもたち、さらには飼育している家畜も含めれば、数えきれないほどの大所帯となります。全員が移動するとなると、大変な時間と労力が必要だったことは想像できます。
では、その旅のペースは誰が決めていたのか。いつ出発して、どこにどれだけの間、留まることにするのか。それは神が決めていたのです。具体的には、神の臨在を示す雲の動きに従って、イスラエルの民は旅立ったり、宿営したりするのを決めていたのです。
荒れ野を旅する間、人びとは天幕(テント)で暮らしていました。その宿営の中には神と会見するための特別な天幕――幕屋――を建てました。この幕屋でモーセは神が語りかけられる声を聞き、幕屋の前ではレビ人が神への献げ物をささげました。
この幕屋を雲が覆っている間、イスラエルの民はその場所に留まり続けました。雲が何日も幕屋に留まり続けても、旅立つことはしませんでした。雲が幕屋から離れて昇ると、人びとは旅立ちました。ときには一晩しか留まらないこともありましたが、それでも主に従って旅立ちました。
「イスラエルの人々は主の命令によって旅立ち、主の命令によって宿営した。」(民数記9章18節)
同じことが20節と23節でも繰り返し語られています。つまり、神の民の理想的な姿として強調されているのは、主の命令に従って歩んだ、ということなのです。
神が示された理想の社会に目を向けて
最近、読んだ本の中で、マッキンダーという人が理想についてこのように語っていました。
「理想化はこの世の中でかけがえのない存在である。これらの人々が我々に刺激を与えてくれなければ、社会はやがて停滞し、文明は衰退の一途を辿るだろう。」※1
理想がなければ人は進歩できず、より良い方向へと変わっていくことができません。かといってそれは現実を見ないで理想論だけを語ればいいということではなく、現実を見なければ理想に向かうこともできません。
聖書には民数記に限らず、人間の本来の姿、あるいは理想的な姿というものが繰り返し語られます。それは天地創造の後、エデンの園で暮らしていたアダムとエバの姿であったり、モーセの律法に定められた人間の姿だったり、預言者たちが伝えた神の約束とそれに答える人の姿だったりします。神と人、人と人、さらに人と被造物との関係が正しく良いものになっている姿が描かれています。
私たちは聖書を通して、一人の信仰者としての生き方を学びます。理想的な姿には程遠いと思うこともありますが、しかしそこに目を向けることによって、一歩ずつ変えられていくこともあるでしょう。個人にとっても道しるべとしても、聖書に描かれた理想は大切です。
それと共に、あるいはそれ以上に、社会の在り方が聖書の理想に向かおうとしているのか、ということも大切なのではないでしょうか。今日の箇所でも、イスラエルの民は個人として主に従ったのではなく、民族としてみんなで主に従っていました。律法では神の御心に沿った社会の在り方が教えられ、預言者は神に背いた権力者たちを批判しました。
日本も含めた世界の多くでは、搾取と収奪が繰り返され、激しくなっているのが現実です。その現実に合わせて理想を捨てるのでは、社会は衰退し、いずれは崩壊します。理想に目を向けて、進む方向を変えていくことが大切です。私たちは、聖書を通して神が示されたこの世界の、また人間社会の理想に目を向けて歩んでいきましょう。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
※1 『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』社會部部長、サンマーク出版、2025年