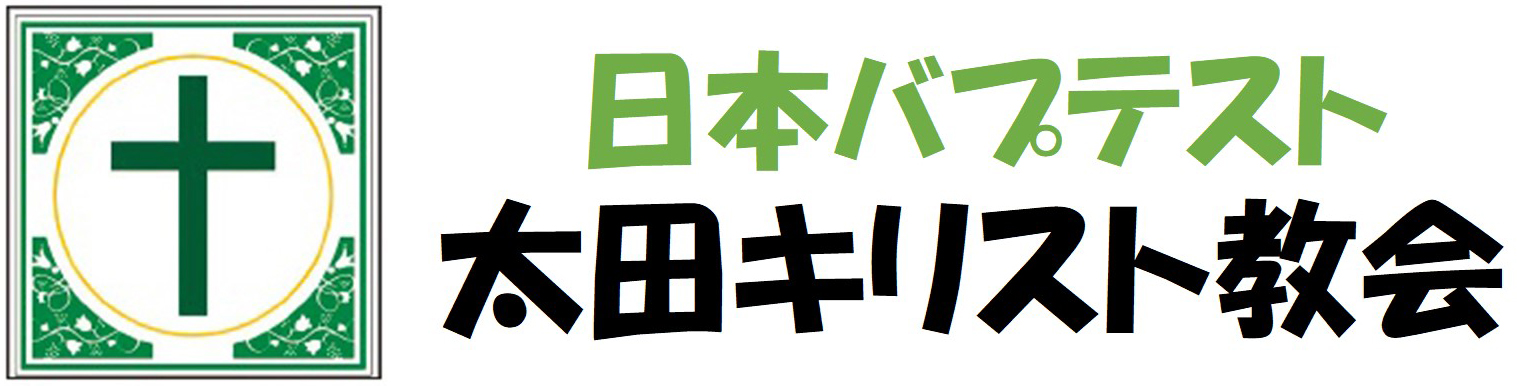礼拝メッセージ(2025年8月31日)「一緒に渡って行くのは誰?」申命記34章1~12節

沖縄から見た「出エジプト」
昨日、「沖縄から宣教を考える会」の公開講演会に参加しました。今回は講師の先生が、沖縄で生まれ育ったご自身の出会いや体験についてお話ししてくださいました。
先生は子どものころから沖縄戦のことを学ぶ機会がたくさんあったそうです。小学校の近くの文化センターには、沖縄戦の時の陸軍病院壕が再現されていました。毎年、戦争体験者の話を聞いたり、実際の映像を見たりする機会もありました。その中で、子どもながら、自分の住んでいる島で多くの人が亡くなったこと、軍によって死を強制された人たちがいたころ、島の少年少女が戦争のために駆り出されたことなども知っていました。
その一方で、戦後の沖縄の歴史や、なぜ米軍基地があるのか、といったことはほとんど教えられてこなかったそうです。生まれた時から米軍基地はあり、戦闘機は頭上近くを飛んでいるのが当たり前で、町中では軍服を着た兵士が歩き、軍用車両が走っている。それが当たり前のことになっていて、基地があることでの苦悩や恐怖には意識が向いていなかったと言います。
先生は、ホテルでお客さんを案内するアルバイトをしていたことがありました。ある時、大型バスに乗ってきた団体がホテルに来ました。その人たちは、手をつないで嘉手納基地の周りをぐるっと囲み、基地に反対するために県外から集まった人たちでした。そのとき初めて「人間の鎖」という行動を知り、沖縄の基地問題のために多くの人が県外から来ることを知ったと言います。
その後、25~26歳のときに牧師を志し、初めて米軍基地に関する本を読み、沖縄がどのような歴史をたどって来たのか、その状況がどれだけ異常であり、日本によって暴力的に押しつけられてきたのか、ということを知って衝撃を受けました。
神学部で学んでいる間も色々な教会での出会いがありました。ある教会では、沖縄に旅行で行って、戦闘機が頭上のすぐ近くを飛んでいて怖かったと言う人がいて、そこで初めてそれが怖いことだったということに気づかされたそうです。またある教会では、90歳近い沖縄出身の婦人と会いました。その方は戦前から日本に来て、名前を変えて“日本人”として生きてきました。教会の方がその方の旧姓を紹介してくれた時、沖縄出身のその方は、「二度とその名前で呼ぶな」と言ったそうです。沖縄の名前を完全に捨てなければ、日本人として生きられなかったのでしょう。
先生はそのようないくつもの出会いを通して、自分は何者なのか、ということ、自分のアイデンティティのことを意識するようになっていきました。沖縄に押しつけられている不条理にだんだんと気づかされながら、同時にその不条理に心を痛める多くの人(県外の人)に出会い、味方がたくさんいることを知っていかれました。
先生の今回のお話の題は「私たちの出エジプト」。沖縄の自分にとって、出エジプトとは脱奴隷、脱支配の物語であり、これまで出会ってきた人たちがエジプトから荒野へと導き出すモーセの働きをしてくださった、と言っておられました。多様な人たちと繋がり合い、影響し合いながら、脱奴隷、脱支配をしていくその先に、主が招かれる約束の地がある、というように、聖書から示されているとお話してくださいました。
神の言葉によって導かれる
出エジプトという出来事は、申命記で一つの区切りを迎えます。エジプトからずっとユダヤの民を導いてきた指導者モーセが、約束の地を前にして死を迎えるからです。ユダヤの民をエジプトから導き出すという神の救いの業にとって、モーセは一番の功労者です。それなのに約束の地に入れないことは、モーセ自身にとっても納得しがたいものだったようで、申命記3章では、約束の地へ渡らせてほしいと主に祈り求めています。
では、ユダヤの人々はモーセの死をどのように受け止めたのでしょうか。もちろん、それは辛く悲しい出来事であり、人々は「三十日の間、モーセを悼んで泣き、モーセのために喪に服し」ました(申命記34章8節)。同時にそれは、約束の地に渡って行くときに、モーセが共にいない、ということでもありました。
モーセは顔と顔を合わせて神と語り合い、人々に神の想いを伝え、また民の想いを神に伝えてきました。民が過ちを犯したときには神に許しを求め、また神を説得して考えを変えていただくこともありました。出エジプトの間、どのようなときもモーセはいつも人々と共にいて、教え、導いてきました。
今日の箇所には、「イスラエルには、再びモーセのような預言者は現れなかった」(申命記34章10節)と書かれています。モーセの死後、ヨシュアという新しい指導者が立てられますが、ヨシュアはモーセと同じ働きができるわけではありません。神と民の間に立って、すべてを担ってくれるような指導者は、もう与えられない。それが大きな転換点です。
これからは、偉大な一人の指導者によってではなく、民に与えられた神の言葉によって導かれていきます。そのために神はモーセを通して掟と戒めを与えられました。その中に神の約束が示され、神の民としてどのように生き、どのような共同体を築いていけばいいか、という指針が示されています。神の言葉を共に聞きながら、一人ひとりが神に応え、従い続けていくことが求められるのです。
背く民でも神は導く
けれどもそれは簡単に実行できることではありませんでした。モーセが共にいたときでさえ、人々はたびたび主に背き、過ちを繰り返してきました。自分たちを奴隷として支配してきたエジプトを懐かしみ、そこに戻りたいとさえ考えました。モーセが共にいたときでさえそうだったのですから、モーセが死んだ後はなおさら、主に背くだろうということは明らかでした。モーセがそのように語っていますし、神も人々がご自身のことを侮り、背くことになるとおっしゃっています。
それでも主はユダヤの人々を約束の地へと導きいれるのです。新しい指導者としてヨシュアを立て、数々の奇跡を起こしながら、人々の新たな歩みを導いていきます。どうせ裏切られるのだから、約束を無かったことにする、とはしないのです。
神が与えてくださった掟と戒めは、祝福を受け取り、恵みを分かち合うための大切なものでした。それを軽んじ、捨ててしまうならば、祝福も恵みも失ってしまうのは当然のことです。それでも、神の側から差し出した手は、いつも変わらず差し出されています。その手を取るように、神の言葉を受け取るように、主の救いに応えて歩むようにと、神は変わらず向き合い続けてくださるのです。
出エジプトの出来事は、はるか昔のことであり、歩んだ荒野の道も私たちの生きている場所とは全く違います。けれども、荒野の旅を終えて、約束の地へ歩みだすユダヤの人々のそばに偉大な指導者モーセがいなくなる、ということは、私たちと共通することです。また、神の教えと導きにも関わらず、何度も神に背いてしまう愚かさも、私たちと同じです。
そして、そのようなユダヤの民を、神がなお約束の地へと導き入れたならば、私たちもまた、神は救いの道へと導いてくださるでしょう。神はいつの時代、どの場所でも、人々を奴隷として支配するところから解放し、生命と平和に満ちた神の国へと導こうとされる方です。
共に渡って行くことができる
そうはいっても、これまで頼り切ってきた指導者モーセがいなくなってしまう、ということは、ユダヤの人々にとって不安なことだったかもしれません。これから川を渡って行く先は、神の約束の地ではあるけれど、自分たちにとっては見知らぬ場所であるし、そこでどのような困難や試練が待ち受けているかわかりません。掟と戒めは与えられていますが、それだけで正しく判断していけるかわからないし、自分たちが神から離れてしまうことも予告されています。約束の地に対する期待もあったでしょうけれども、不安や恐れを抱く人がいても不思議ではありません。
「私たちはこれからどうなってしまうのか」。そのような不安や恐れは、ユダヤの人々にとっても、また私たちにとっても無縁なものではありません。向こう側へと渡って行くことは、不確かで、頼りなく感じ、心細いものでしょう。そのようなときに、モーセを通して主から与えられた約束がありました。
「強く、また雄々しくあれ。恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神、主は、あなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも、見捨てられることもない。」(申命記31章6節)
出エジプトの間、荒野を旅するときに共にいてくださったように、主は今も、そしてこれからも、私たちと歩んでくださる。私たちが渡って行く新たな場所、あるいは私たちが向かい合う新たな出来事に、期待と不安が入り混じるようなところで、主は共にいて、私たちと共に渡って行ってくださるのです。主はあなたを見放すことも、見捨てられることもない。だから恐れてはならない。
その主はまた、私たちが一人にならないように、共に渡って行く人や、渡って行った先で出会う人をも与えてくださいます。ユダヤの民は、みんなで一緒に渡って行きました。その中にはユダヤの民だけでなく、多様な人たちが含まれていました。人々は時に過ちを犯しながらも、共に語り合い、学び合い、支え合い、祈り合いながら、進んで行ったのでしょう。
私たちもそれぞれの人生の中で色々な出会いが与えられています。教会にも多様な人が集います。私たちもまた、語り合い、学び合い、支え合い、祈り合いながら、神の示された約束の地へ、救いと解放に向けて、一緒に渡って行くことができる。それも主の恵みなのではないでしょうか。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
『現代聖書注解 申命記』P.D.ミラー、日本基督教団出版局、1999年