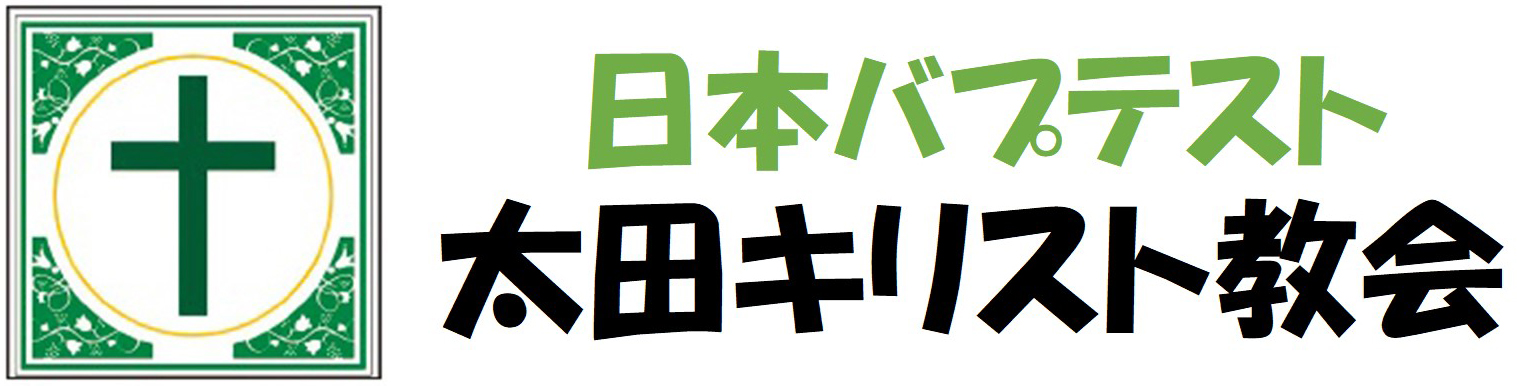礼拝メッセージ(2025年9月14日)「進むべき道を知るために」ヨシュア記3:1~17

立ち返るべき物語
超教派の団体の一つに「世界教会協議会(The World Council of Churches、略:WCC)という団体があります。WCCでは9月1日から10月4日までの期間を「被造物の季節」としています。この期間に、気候変動や生物多様性の喪失、環境正義について教会で教え、そのことを覚えて礼拝をささげ、創造主である神と被造物との関係を新しくすることを祈り、行動をするように呼びかけています。
「被造物の季節」が始まるにあたり、バルトロメオ総主教は、環境破壊と地球規模の暴力がどちらも地球上の生命を脅かしていると警告して、「地球上の生命の未来は、環境に優しく平和なものになるか、あるいは存在しなくなるかのどちらかだ」と述べました。そのためには、環境破壊に対する単なる反省にとどまらず、むしろ「被造世界に対する考え方と行動の根本的な変化」が必要だと主張しています。
日本バプテスト連盟や世界バプテスト連盟でも、環境破壊や気候変動のことは話題になりますが、まだ真剣に向き合えているとは言えません。それでも、私たちも既に経験しているように、地球環境は加速度的に変化をしており、多くの生命を奪い始めています。
このような状況の中でこれからのことを考えるときに、私は「なぜこんなことになってしまったのか、どうすればよかったのか」ということを問わずにはいられません。何か根本的な過ちがあったのだとすれば、そのことを悔い改め、進むべき道を変えなければ、生命を守り、神からいただく祝福を分かち合い、受け継ぐことはできないと思うからです。
ヨシュア記は、バビロン捕囚を経たユダヤの人々が取りまとめたものだと考えられています。そのときにはユダヤの人々も「なぜこんなことになってしまったのか、どうすればよかったのか」、という問いを持っていました。先祖が経験した主の奇跡の中に、立ち返るべき信仰の姿勢を見出した物語として、今日の箇所を読みたいと思います。
※”WCCが全地総主教バルトロメオ1世に賛同 「被造物の季節」にあわせ 2025年9月3日”https://www.kirishin.com/2025/09/03/79593/(参照2025-9-13)
主が起こされた奇跡
ここでは、ヨシュアとユダヤの人々がヨルダン川を渡り、いよいよ約束の地へと踏み入ります。出エジプトから続いた長い旅の目的地にようやくたどり着こうとしています。しかし、ヨルダン川はとても流れの速い川です。特に春の借り入れの時期は水量が多く、川岸から水が溢れそうになるほどです。この川を徒歩で無事に渡りきることは不可能に思えます。
そこで主は、祭司たちに契約の箱を担がせて、人々に先立って川を渡らせました。契約の箱には、モーセが主から授かった十戒の板が納められていて、そこに主が臨在しておられるしるしとなりました。その契約の箱が先立って進むということは、主が人々に先立って進んで行く、ということです。
契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の水際に着きました。そして彼ら川の水に足を踏み入れると、川の水がはるか上流でせき止められ、壁のように立ちました。ヨルダン川は干上がり、ユダヤの人々は全員、川床を歩いて安全に渡り終えることができました。
それは主が起こされた奇跡でした。葦の海を二つに分けてモーセたちを渡らせたときの奇跡にも似ています。エジプトからの脱出、荒れ野での長い旅、そして約束の地に踏み入ること、それは人間の力によるものではなく、主によって起こされた奇跡であることが、改めて告げられているようです。
神は聖なる方であるということ
この箇所の中で違和感のある言葉がありました。それは4節の言葉で、主の契約の箱の後に続いて来ることに加えてこのように命じられました。
「契約の箱との間には約二千アンマの距離をとり、それ以上近寄ってはならない。そうすれば、これまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道は分かる。」(ヨシュア記3章4節)
2千アンマというのは、900mほどの距離です。先に進んで行く姿を目で見ることはできるでしょうけれども、一緒にいるとは感じにくい距離です。「これまで一度も通ったことのない道」を進んで行くのですから、もっと近くにいた方が迷う心配もないでしょう。それでも、900mよりも近寄ってはならない、と言われています。
このように距離を取ることを求められるのは、主が聖なる神であり、契約の箱も聖なる物とされているからです。“聖”という言葉によって、神の超越性が強く表現されています。神は決して人間の手の中に納まるようなお方ではない。人間の考えや想いの中に留まるようなお方でもない。神は私たちを超越しておられる方であって、畏れ敬うべき方です。
神は人と出会い、人の間に下り、人を導く方です。主イエスが人となってこの世を生きられたように、私たちの友となってくださる方です。でもそれは、神が聖ではなくなった、ということではありません。ホセア書11章9節では、「わたしは神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって聖なる者」と語られています。神の子が人となったということは奇跡ですが、神が聖なる方ではなくなったとか、神であることを辞めて人間になった、ということではありません。
聖なる神は、どのようなときも妥協せず義を求めます。人間は妥協もすれば、諦めもします。けれども神は正義と真理をないがしろにすることはなく、神の義を果たし、救いをもたらし、平和を成し遂げることを手放そうとはなさりません。そのために聖書ではしばしば、厳しいと感じられるような命令がなされています。
そのため、今日の箇所について、註解書ではこのように書かれていました。
「神は民のもとに来て導くが、同時に神は人を寄せ付けないほど聖なる存在であることを人間は知らなければならない。」*1
神を軽んじてはならない。神を侮ることは許されない。神は愛の神であり、私たちの下に降ってきてくださり、ご自身の命さえ差し出してくださる方ですが、神が聖なる方であることは決して失われることがありません。だから、神を畏れ敬うということを忘れてはなりません。契約の箱との距離は、そのようなことを現わしているように思えます。
「聖なるもの」の変化
そのようなことをお話するために、昨日の夜まで考え、準備をしていましたが、あまりうまく説明ができないと感じています。神が聖なる方である、ということ、旧約聖書の人々と神との距離感のようなものが、直感的に理解できないからかもしれません。
それはなぜだろうかと考え、調べてみたところ、その理由を二つほど見つけました。一つは日本の文化や伝統的な宗教では、聖なるものと俗のものとの境界線がはっきりとはされていなかった、ということがあります。日常生活と宗教的な行為が重なっていて、聖なるものや領域があっても、あまり明確に分けようとはしてこなかったようです。
もう一つは近代化の影響です。キリスト教社会であった欧米では、教会と国家が二つの権威になっていて、神の領域と人間の領域とが明確に区別されていました。近代に入ると世俗化が進んで教会の力は弱まり、信仰は個人の事柄に変わっていきました。戦後の日本も世俗化した欧米の影響を受けています。葬式が宗教とは無関係に行われたり、祭りが観光資源として利用されたり、教会が観光スポットになったりして、宗教性がどんどん薄れています。一方ではパワースポット巡りが流行るなど、聖なるものや場所が触れてはいけないものではなく、気軽に体験できるようなものにもなっています。
近代以降、社会の中心は神の意志ではなく、人間の理性へと変わっていきました。人間中心主義が広がり、浸透していったことで、以前は聖なるものとされていたものも、人が近づいていいものになり、個人のために利用してもいいものに変わっていった。そのような社会の中で生きている私には、ヨシュアたちのような聖なる方との距離感が理解しづらくなったのかもしれません。
人間中心ではなく、神を聖とすること
近代化によって得られたものや新たに発見したことはいろいろあったと思います。また、巨大な権力をもった教会が過ちを犯したこともあり、聖と俗を分けることで正当化されてきた差別や抑圧もありました。だから、変わってきたことの中には良いこともあったと思います。
けれども、あらゆる領域に人間中心主義が広がり、その反面、聖なるものへの態度が変わってきたことは、問題があるのではないかと思わされています。
環境破壊や気候変動もその一つです。様々な社会には聖なる領域があって、そこには気軽に立ち入れなかったり、利用することが制限されていたりしました。それが自然を保護し、環境を守ることにもなっていました。しかし今では人間が利用してはならないとされている場所は皆無といえるほど、地球上の隅から隅まで人間の利益のために――それも一握りの人間の利益のために――利用し尽くされようとしています。そのことで、現地に住む人に健康被害が出ても、生物が生きる場所を失っても、将来の世代に大きなつけが残されることになっても、まるでお構いなしです。
このような道を歩き続けるわけにはいきません。生命を守り、神からいただく祝福を分かち合い、受け継いでいくためには、進むべき道を変えなければなりません。しかしこれから進む道は、「これまで一度も通ったことのない道」となるかもしれません。それでも、「あなたたちの行くべき道は分かる」と主は言われます。どうすればいいのですか、という問いへの答えは、契約の箱との間に距離を取ること、言い換えると「神を聖とすること」です。
人間中心主義から立ち返って、神の意志を求め、神の後に従うこと。この世界は何でも人間が自由に利用していいわけではなく、手を出してはいけないことや、制限しなければならないことがあることを知ること。人間の思いではなく、神の御心が実現することで祝福が得られること。そのようなことに立ち返っていくことが必要です。
現代に生きる私たちが、ヨシュアと同じように「神が聖である」と理解し、行動できるようになるわけではないでしょう。それでも、神は聖なる方であることを覚えていくことは大切です。そのことを奇跡的な体験で気づかされるのか、あるいは科学的な観点から気づかされるのか、それは一つではないかもしれません。いずれにしても、教会は神を聖とすることの大切さ、人間中心ではない道を伝えていきたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
*1『ATD旧約聖書註解(5/2)ヨシュア記・士師記・ルツ記』ハンス・ヴィルヘルム・ヘルツベルク、ATD・NTD聖書註解刊行会、2000年
『旧約聖書神学概説』TH.C.フリーゼン、日本基督教団出版局、1969年
※Squirrel_photosによるPixabayからの画像