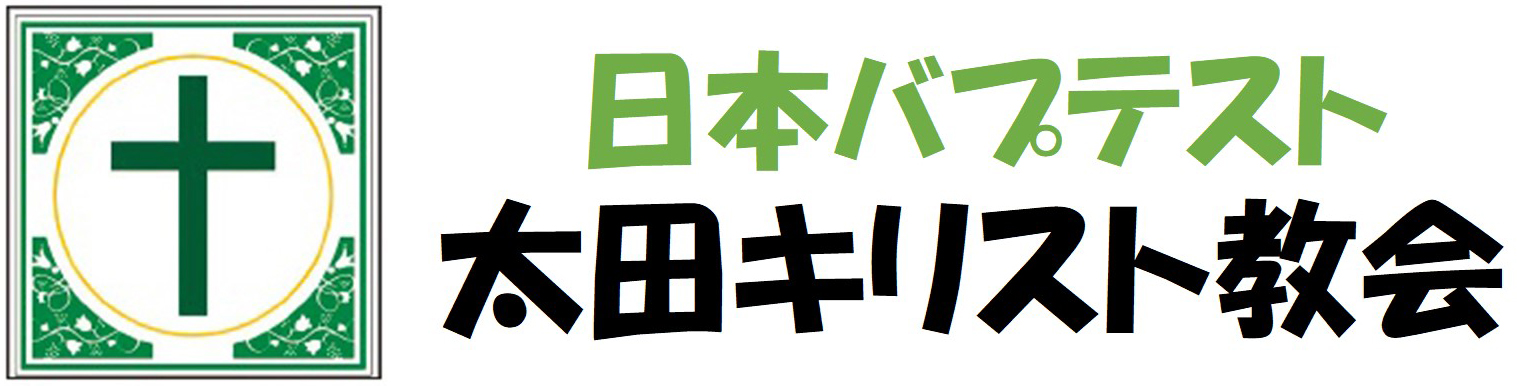礼拝メッセージ(2025年9月21日)「最悪の事態を避けるために」ヨシュア記20:1~9

報復の連鎖を避けるための制度
ヨシュア記では、19章までにユダヤの民は約束の地に侵入し、部族ごとに土地の配分を終えています。神の民としてそこで生活する上での指示が20章には書かれています。それは「逃れの町」を定めることです。「逃れの町」は、「過って人を殺した者がそこに逃げ込めるように」するための場所です。そのような場所が必要とされたのは、古代ユダヤ人の共同体には「血の復讐」という慣習があったからです。
「血の復讐」とは、誰かが殺害されたときに、犠牲者の息子や兄弟、あるいは近親者が殺人を犯した相手を殺害することです。それは裁判もなしに私的に行われる処罰であり、犠牲者やその家族の名誉のために行う義務がある、とされていました。もちろん、家族を殺害されたことへの怒りや憎しみも、復讐の動機になったことでしょう。
このような慣習は、世界の様々な民族や文化にもあったものです。ヨーロッパにも、アラブ社会にも、中国にもありましたし、日本でも江戸時代までは「敵討ち」が武士の名誉行為として認められていました。国家による法の支配が弱い社会では、「血の復讐」が社会の秩序維持や名誉回復の手段となっていたようです。
ただ、私的に行われる復讐では、報復の連鎖を産む危険性が高まります。そのため、それぞれの文化では、賠償や和解儀礼、法による裁きなどを行うことで、「血の復讐」を制御するようになりました。「逃れの町」も同じような目的があるでしょう。
ここで扱われているのは、本人が意図せずに、誤って誰かの命を奪ってしまった場合のことです。その人が逃れの町まで逃げ込んできたら、町の長老たちが事情を聞きます。その事情が受け入れられるものであれば、誤って命を奪ってしまった人を保護して、被害者の一族による復讐が行われないようにしました。
命を奪ってしまった人は、共同体の前に出て裁きを受けるまでか、あるいはその時の大祭司が死ぬまでの間、逃れの町に留まらなければなりません。保護されるのは町の中にいるときだけなので、自由は制限されています。
このような逃れの町の機能が、6つの町に設定されました。与えられた土地のどの町からも、歩いて1日のうちに逃げ込める距離となるように、逃れの町は配置されたようです。報復の連鎖が続き、犠牲者が増え、共同体が危機に陥ってしまうような最悪の事態を避けようとする意図がここから感じ取ることができます。
過剰な報復が行われる現実
報復の連鎖を制限するものとしては、ハンムラビ法典の中の「目には目を、歯には歯を」という言葉が有名です。ハンムラビ法典は約4000年前に制定された最古の法典の一つです。「目には目を、歯には歯を」という言葉は、加害者から受けた被害と同じ大きさだけの罰を与える原則を表しています。それは過剰な報復がなされないための歯止めでした。旧約聖書もその影響を受けており、「目には目を、歯には歯を」という言葉が出エジプト記とレビ記、申命記の中にも見つかります。
現代の私たちから見ると、逃れの町の設定も、ハンムラビ法典の規定も、不十分なものに思えるでしょう。いずれも部分的には復讐を認めているようにも見えます。そのようなものになったのは、人が抱く復讐心が強く、復讐のすべてを抑制することが難しかったからかもしれません。そのため、段階を踏んで、許容されるところから始めたのではないかと想像します。
復讐心は現代社会でも共有され得る感情です。人間は不正や裏切りに対して怒りや報復感情を持ちやすいことが確認されています。映画やドラマ、漫画などでは、殺人犯の動機が復讐することであったり、ヒーローが家族の仇を討つために立ち上がったりする物語がよく見られます。それだけ復讐心は現代でも共感され、理解されやすいのでしょう。
今は裁判制度や法律が整えられ、加害者には罰を与える一方で私的な復讐は禁じられています。キリスト教や他の宗教も、報復の連鎖を断ち切るように教えてきました。それでも、過剰な報復がなされることはあります。特に圧倒的な力をもった国家の報復は目に余ります。
一昨年の10月7日、イスラム組織ハマスがイスラエルに仕掛けた攻撃では、約1200人が殺害され、251人が連れ去られました。これは戦争犯罪だとして非難されています。これに対してイスラエルが始めた報復攻撃は、来月で2年を過ぎようとしています。ガザ地区での犠牲者は6万5千人を超えました。それも報告されている人数であり、実際はもっと多いだろうとも言われています。
先週、国連の人権理事会の調査委員会が、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対してジェノサイド(集団殺害)を行っていると認定しました。これまで、国際的な人権団体からも、またイスラエル国内の人権団体からも、イスラエルが行っていることはジェノサイドであると非難されてきました。ハマスの攻撃への報復が、ガザの住民に対するジェノサイドだというのは、あまりにも不釣り合いです。「目には目を、歯には歯を」という古代の基準さえもはるかに超えた過剰な報復が行われる現実を見せつけられています。
失われたものの回復を目指す「報復の神」
「逃れの町」を設定することは、最悪の事態を避けるための手段としては、不十分で小さな一歩に過ぎないかもしれません。それでも、復讐心に捕らわれ、それを煽り、過剰な報復を行ってしまう現実の中では、そのような進み方しかできなかったのかもしれません。愚かな人間の不完全さに対して、神が忍耐をもって導こうとしておられるようにも思えます。
それは消極的な前進ですが、聖書にはもっと積極的なことも語られています。例えば詩編94編の言葉です。
「主よ、報復の神として/報復の神として顕現し
全地の裁き手として立ち上がり/誇る者を罰してください。」(詩編94編1~2節)
「報復の神」という呼び方はこの詩に特有なものです。ここでの「報復」には、誰かを憎み、やられた分をやり返す、という感情的な意味は含まれていません。反撃するとか、仕返しするといった、日本語の「報復」という言葉が持っている意味で、「報復の神」と呼んでいるわけではありません。その点は日本語で聖書を読むときに分かりづらく、誤解しやすいことです。
報復が神に求められるのは、5節から7節にあるような状況です。
「主よ、彼らはあなたの民を砕き/あなたの嗣業を苦しめています。
やもめや寄留の民を殺し/みなしごを虐殺しています。
『主は見ていない。ヤコブの神は気づくことがない』と。」(詩編94編5~7節)
主に逆らう者が勝ち誇り、主の教えてくださった秩序が破られ、弱くされた人々が虐げられ、生命を奪われている。そのような時に主に願い求める「報復」は、14~15節に語られているようなことです。
「主は御自分の民を決しておろそかになさらず
御自分の嗣業を見捨てることはなさいません。
正しい裁きは再び確立し
心のまっすぐな人は皆、それに従うでしょう。」(詩編94編14~15節)
求められたのは、正しい裁きが再び確立すること。言い換えれば、社会や共同体の秩序が回復し、主が教えてくださった律法が再び守られ、主の正義が行われるようになること。それが主のなさる「報復」なのです。つまり、報復とは傷つけ、奪うことではなく、失われ、損なわれたものを回復すること、社会や共同体の健全さを回復することなのです。
罰を与えることは、将来に起こり得る犯罪を抑止することに一定の効果はあります。けれども過ちを犯した人に罰を与えることだけでは、失われたものが回復することはありませんし、社会や共同体を健全なものに建て上げていくことはできません。
「報復の神」と呼ばれた主は、復讐の連鎖を引き起こすような方ではありません。神の目的は失われたものの回復であり、御心に適った創造の完成です。罪によって損なわれた関係性を回復することも、主の目的であり続けています。
隣人を愛することに向かって
主の目的は、最悪の事態を避けるだけでなく、そこからの回復にも留まらず、さらに積極的な関係へと向かっていることも聖書には語られています。
「復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。」(レビ記19章18節)
これは主がモーセに教えられたことですが、イエスの教えとも重なっています。復讐心を手放す。恨みや憎しみの連鎖を断ち切る。そこからさらに進んで、自分自身を愛するように隣人を愛する。それができれば、壊れた関係が回復するだけでなく、さらに深められ、隣人と共に生きることができるようになるでしょう。
逃れの町で行われることを振り返ると、加害者と犠牲者の一族だけで問題を扱うのではなく、逃れの町の長老たち、さらには町の住人たちが関わるようになっていました。長老たちは逃げ込んできた人の話を聞きますし、その人が町で生活するなら、町の住人たちの協力も不可欠だったでしょう。そのような中で、その人のことを知っていくことになります。
隣人を愛するには、その人のことを知らなければ始まりません。知ろうとすることが既に愛することの始まりだと言えるのかもしれません。逃れの町では加害者と町の人々との関わりしか見えませんが、犠牲者の一族の人々のことも知り、さらには加害者側と犠牲者側がお互いのことを知っていければ、なお良いでしょう。知ることを通して、愛が生まれ、憎しみが変えられていくかもしれません。
最悪の事態を避けるために逃れの町が設定されたように、最悪の事態を避けるために必要なことは今でもあるでしょう。それと共に、失われたものを回復していくこと、さらには復讐心を手放し、隣人を知り、愛することへと向かっていくことも大切です。愛することは難しいと感じることも多いですし、知ることさえ簡単ではないかもしれません。それでも、それが大切なことであった、ということ、主が教え示してくださったことであることを、共に覚えたいと思います。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
『ATD旧約聖書註解(5/2)ヨシュア記・士師記・ルツ記』ハンス・ヴィルヘルム・ヘルツベルク、ATD・NTD聖書註解刊行会、2000年
『旧約聖書Ⅱ歴史書[机上版]』旧約聖書翻訳委員会、岩波書店、2005年
『旧約新約聖書大辞典』旧約新約聖書大辞典編集委員会、教文館、1989年
『現代聖書註解 詩編』J.L.メイズ、日本基督教団出版局、2000年
※DreamdeckoによるPixabayからの画像