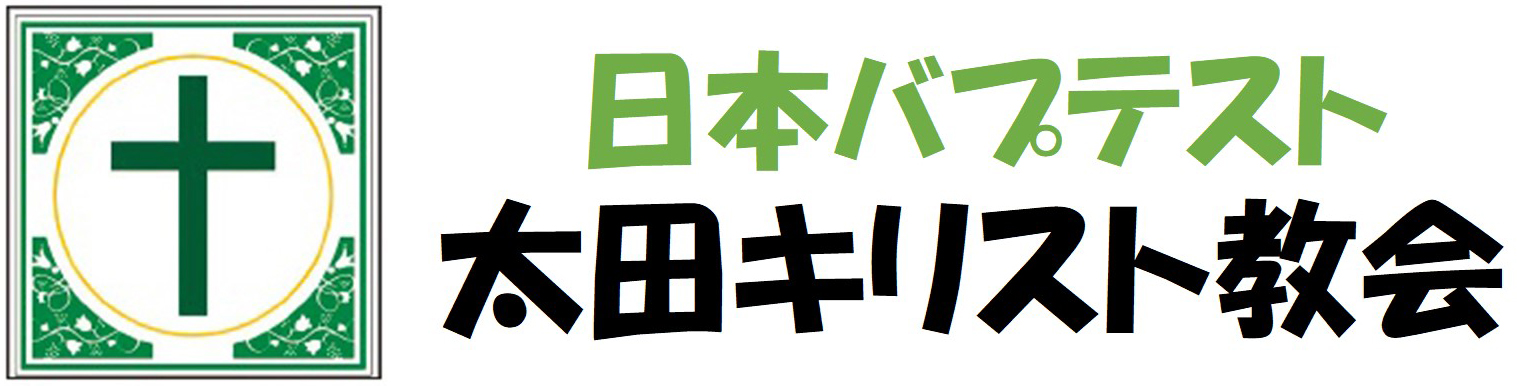礼拝メッセージ(2025年9月28日)「だから主に仕えます」ヨシュア記24章1~15節

主に仕える理由
ヨシュア記は、約束の地での定住の始まりを描いています。ヨルダン川を渡り、部族ごとに土地の配分を決め、逃れの町を定めました。そこから長い年月が流れ、ヨシュアの生涯が終わろうとしているときに、ヨシュアはユダヤの人々を集め、告別の言葉を語りました(ヨシュア記23章)。そして今日の箇所では主なる神からの言葉を民全員に告げ、これからも主に仕えるように教えました。
新しい地で生活を始めたユダヤの人々にとって、誰に仕えて生きていくか、ということは重要な問題となります。約束の地カナンではバアルなど他の神々が信仰されていました。そのような中で、これからも主なる神に仕え続けることができるかどうか、ということが問われたのです。
24章で主から語られた言葉には、主に仕えるべき理由が語られています。主はアブラハムをユーフラテス川の向こうから連れ出し、その子孫を増し加えました。主はモーセとアロンを遣わして、エジプトで奴隷とされていた人々を導き出しました。後を追ってきたエジプト軍を退け、荒れ野での長い旅を守り、約束の地を与えてくださいました。
ここで繰り返されていることは、それらのことは主がおこなってくださったことである、ということです。今、約束の地で豊かな生活を送ることができるようになりましたが、そこは「自分で労せずして得た土地」であり、人々は「自分で建てたのではない町」に住んでおり、「自分で植えたのではないぶどう畑とオリーブ畑の果実を食べている」のです。
一言で言い換えるならば、すべては神の恵みであった、ということです。神が選び出し、神が導き、神が守り助け、神が与えてくださった。自分たちの手でできることをはるかに超えて、奇跡を起こし、今、新しい地での生活を始めることができている。主なる神の祝福を受けて、たくさんの恵みを受けている。主に仕える理由がそこにありました。
「あなたたちはだから、主を畏れ、真心を込め真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を除き去って、主に仕えなさい。」(ヨシュア記24章14節)
これまであなたたちを特別に愛し、助け導いてくださったのは、新しく出会った他の神々ではなく、ずっと共にいてくださった主なる神でした。だからこれからも主に仕えなさい。他の神々を主と並べるのではなく、主にのみ仕えなさい。それが恵み深い主への感謝の応答であり、主に呼びかけられた者がなすべきことなのです。
他の神々に仕えるということ
カナン地方で広く礼拝されていた“バアル”と呼ばれる神は、天候と豊穣の神とされていていました。ユダヤの人々は、16節では力強く「主を捨てて、ほかの神々に仕えることなど、するはずがありません」と宣言していますが、現実にはバアル宗教はユダヤ社会に広まってしまいました。
ヨシュア記が現在の形にまとめられたのは、ヨシュアの時代よりずっと後、南ユダ王国が滅亡し、バビロン捕囚が行われた後だと考えられています。そのためヨシュア記の背後には、「神から授かった約束の地を失ってしまったのはなぜなのか」、という問いがあります。ここでのヨシュアとユダヤの人々の言葉がこのように書き残されたのは、他の神々に仕えてしまったことが災いを招いた原因だったという後代の人々の反省があったからです。
では、私たちにとって、バアル信仰とはどのようなことになるでしょうか。私たちが生きている近代文明では、宗教は社会と切り離され、個人の心の中の事柄とされています。このような社会の中で、「他の神々に仕えてはならない」という言葉を聞くと、それぞれの心の中で誰を神として思い浮かべるか、ということに限定されてしまいそうです。
しかし、旧約聖書の信仰も、バアル信仰も、現代とは違って宗教が社会全体と密接に結びついていました。バアル信仰は雨を降らせ、収穫を与える保証を与えるもので、豊かな収穫を得られるようにと祈る儀式が行われていました。それは富や経済活動、また社会秩序や権力と結びついていました。
旧約聖書の律法は、古代イスラエル社会における政治や経済、文化にも関わる戒めでした。個人の信仰に留まらず、社会・共同体をどのように運営し、秩序付け、また互いを結び合わせ、誰が権力をもち、それをどのように用いるか、ということを定めていました。バアル信仰もまた、個人の事柄に留まらず、社会の在り方や方向性を定めるものとなっていました。
つまり、誰に仕えるかという問題は、個人の心の中の信仰には留まらない、ということです。その社会における政治、経済、文化に関わる全体の事柄、人間の生きるあらゆる領域において、誰の言葉を聞き、何を信頼し、誰に仕えていくのか、ということが、ここでは問われていた、ということです。
現代のバアル
このように考えた時、主に仕えるか、他の神々に仕えるか、という問題は、ヨシュアの時代に重要であっただけでなく、現代においても重要な問題となります。現代の「他の神々」は、他宗教の神々のことだけではなく、むしろ宗教以外のものにこそ当てはまるかもしれません。
例えばお金も人を仕えさせる力があります。資本主義社会では、人のつながりは奪われる一方で、あらゆることにお金が要求されるようになっていきます。お金を稼ぐことが人生の目的であるかのようにされたり、生きるためにお金を追い求めなければならなくなったりします。
あるいは科学技術も大きな影響を与えています。技術の発展によって改善したこと、助かった命もたくさんありますが、問題は技術によって解決するという理解が広まり、神への信仰を不要だという見方が生まれました。一方で、日常のあらゆることが科学技術に依存してしまって、人がそれに捕らわれたり、追われたりすることもあります。
さらには、国の枠組みの中で人が支配され、仕えさせられるものもあるでしょう。法律は守るべきものですが、入管法のように人を抑圧し、人権を踏みにじるようなものもあります。教育は重要な働きですが、ブラック校則のように子どもたちを無駄に縛るものもあります。戦争をすることになれば、軍事的な体制に仕えることが強要されることもあるでしょう。
現代の日本では、それらと宗教が結び付けられることは多くないかもしれません。それでも人がそれに頼り、仕えようとしたり、あるいは強制的に仕えさせられたりするようなことがあるならば、それは現代における“バアル”だと言っていいかもしれません。主なる神ではないものに仕えさせようとする力は、現代においても働いています。
しかしそれは、私たちを生命へと導き、祝福を与える神ではありません。私たちを愛して、恵みを与えてくださる存在ではないのです。むしろそれらを利用して他者を支配し、利用しようとする人がいますし、それによって犠牲にさせられる多くの人がいます。そこが主なる神との違いです。宗教的であるか否か、ではなく、私たちをどこからどこへ導き、何を与えようとするのか、ということが、仕えるべき方がどうかの違いになるでしょう。
与えられていた恵み
ヨシュアたちが主に仕えるのは、主から命令されたから、というのではありません。ヨシュアたち自身も、またその先祖も、ずっと神に導かれ、恵みを与えられてきたからです。主に愛され、主が共にいてくださった。だからヨシュアたちは主に仕えることを選びました。そうするべきであったと後代の人々は思い直したのです。
私たちも主に愛され、主からたくさんの恵みをいただいてきました。だからこそ、私たちは主に仕えて歩んでいくのです。それぞれの生涯を振り返り、既に与えられてきたもの、自分の手によらずに得られたものを思い起こし、感謝をもって主に仕えるのです。
ただし、与えられたものとは個人的なものばかりではありません。ユダヤの人々や約束の地を与えられましたが、その土地が豊かであったのは、その土地の気候や生態系が人にとって良い環境であったことと、そこに長い間暮らしてきた人々が、井戸を掘り、町を作り、畑を耕し、ぶどうやオリーブを育ててきたからです。
土を通して植物は栄養や水を吸収して育ち、他の生き物の食料になります。土の中には無数の微生物が存在していて、他の生き物の排泄物や落ち葉などを分解して、植物の栄養に変えています。そのような土は、人間にはつくることができません。ティースプーン1杯の土の中には、何十億もの微生物が見つかるそうですが、そのような微生物や小さな生き物が土を作っています。それはとても長い時間がかかるもので、1㎝の土を作るのに100年も1000年もかかるそうです。
近代の日本では、本州から北海道に入植活動が行われました。気候も異なり、見ず知らずの土地でしたが、先住民族であったアイヌの人々から多くのことを学びました。魚の取り方、食べられる植物のこと、履物や熊対策など、アイヌの生活の知恵によって助けられていたようです。
それらはほんの一例にすぎませんが、現代社会も実は多くのものを与えられて成り立っています。与えられたものがあること、恵みであったことを忘れてしまっているだけです。より大きな富や力をもった人が、何でも自由にできる社会になってしまったことで、他の人や生き物から与えられているもの――あるいは奪ってきたもの――が何か、わからなくなっています。そうなってしまうと、主から与えられた恵みもわからなくなり、主に仕えようとすることも失われてしまうのではないでしょうか。
近年、「持続可能性(サステナビリティ)」という言葉をよく聞くようになりました。それは裏返せば、今のような社会、今のような生活は、持続可能ではない、ということです。ユダヤの民は、約束の地での生活が続くためには、与えられていた恵みを思い起こして、主に仕えることが大切だったということを発見しました。私たちの社会も、与えられていた恵みを改めて発見することが必要です。そして、恵みを与え、生命へと導いてくださる主に仕え、異なる人々、異なる生き物とも共に生きていくことへと向きを変えていくことが求められています。
牧師 杉山望
※このホームページ内の聖句は すべて『聖書 新共同訳』(c)日本聖書協会 から引用しています。
(c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
参考書籍
『ATD旧約聖書註解(5/2)ヨシュア記・士師記・ルツ記』ハンス・ヴィルヘルム・ヘルツベルク、ATD・NTD聖書註解刊行会、2000年
『奇妙で不思議な土の世界』英国王立園芸協会、創元社、2024年
遠軽町役場.”アイヌと開拓者の関わり”.えんがる歴史物語.http://story.engaru.jp/story/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%A8%E9%96%8B%E6%8B%93%E8%80%85%E3%81%AE%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8A/,(参照2025-09-27)